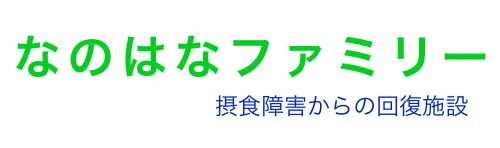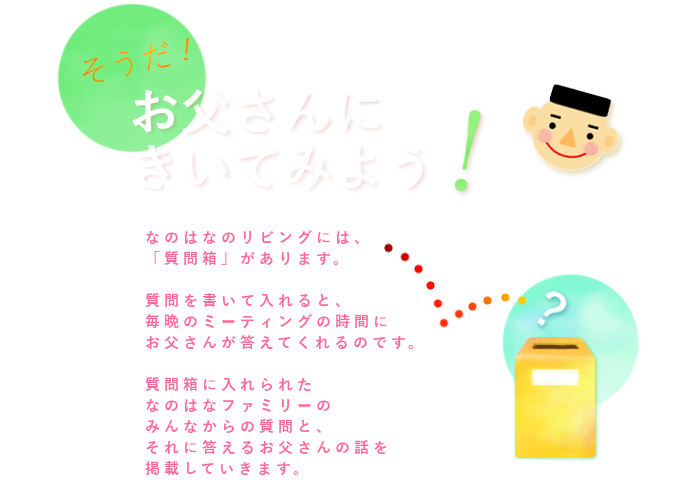
第16回「不安の先取り」

質問
不安の先取りは、なぜしてしまうのですか?
毎日起こることや、始まることを次々に、不安、心配の種にして、自分で自分を重たくしてしまっています。
でも、楽観的に前向きに、一生懸命に向かおうと思います。
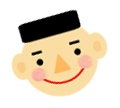
答え
苦しくなった人は、みんなそうですね。どんどん不安の先取りをしてしまいます。
自分がうまく物事に対応できないとか、うまく処理することができないだろうっていう、悲観的な気持ちがあるんですね。
それをきっと楽しめないだろうとか、きっとやれないという否定的な考えしか浮かんできません。
苦しさを得てから、何をやっても苦しいことだけだったのです。だから、何か新しいことやるのが、特に嫌になります。
何をやっても、できないことを人から責められているような気持ちがしてしまうんです。実際に失敗した体験とか、叱られた体験とか、自分で情けない体験が強く残りすぎていて、もう失敗したくないのです。
人が自転車に初めて乗るとき、練習をします。このとき、主に小脳が働いていると言われています。自転車は、最初は乗れません。よろけたり、倒れたりしてしまいます。なかなかうまくこげない。
そうやって練習しているときに、こうやったら失敗するよ、こうやったら、今度はこういう失敗という情報が小脳に行き、だから、こういうことはやっちゃいけないっていう情報がたまっていくとだんだん成功するほうに近づいていきます。
たまたまうまくいくと、それはやってもいいということになるだけで、成功体験を覚えているんじゃなくて、失敗体験をしないようにする。
失敗体験をしないように小脳が仕向けて、自転車に乗れるようになると言われています。自転車に乗りたければ、早いうちにたくさん失敗して、いっぱい失敗を経験したら、もう失敗しないようにしよう、で乗れるようになる。
今、自転車を乗ることに例えましたが、生きている日々の行為の中で、苦しさを抱えた人は失敗ばかりしているわけです。
だから、新しいことに挑戦しても、うまくいくとはとても思えない。いろんなことがね。
自転車だったら、目的が乗ることってはっきりしていますが、畑作業だと、目的や手段が次々変わりますよね。だから、それに対応できる気がしないのです。でも、人が生きていくことはこういう応用問題みたいなものばかりなのです。
僕はよく、「アスペルガー的な発想」とか言いますが、摂食障害になる人は、アスペルガーの人が多いです。
しかも、摂食障害の人はアスペルガーでなくても、アスペルガーと同じような行動になって行く人が多いです。
アスペルガーの人の究極の特徴は、統合力がない、ということです。
認識、記憶、考える、この3つの脳の機能を統合して同時平行で処理することに弱いのがアスペルガーで、どれか一つになってしまって3つの機能の連携がとれません。苦しくなると、そんなふうにどんどん統合力がなくなっていきます。
本物の、自閉症の人は、やっぱり、不安の先取りどころか、生きていくことに不安だらけなんです。3つが連携せずに、認識だけしかできないとか、記憶だけしかできないとか、考えるだけしかできない、となってしまいます。
そうすると、必ず失敗するし、世の中がどう回っているかつかめないので、とても不安になるのです。
自閉症の人は不安にならないためにどうするかというと、方法が一つだけあるんです。
日々の行動を全て同じにしてしまうことです。そうすると、よく分からないことが.自分の中から消すことができます。
同じ時間に寝て、同じ時間に起きて、同じところに座り、同じ時間に食べる。
でも、家族が別なところに座ると、不安になるので、ミニカーとかを机の上にいつもと同じように並べて、同じ状況を作る。
同じものを食べる。おかずとかが毎日、変わると怖いから、白米しか食べない、となったりもします。同じ手順で同じことをやると、不確定要素がなくなるので、まあ安心できる。そうやって、自分の不安を消していくことが多いです。
摂食障害の人は、苦しくなると、色んなことが不安になって、非常にしばしば自閉症の人と同じ行動をとるようになります。
今くらいの時間になると、スーパーで割引のシールが貼られます、すると、過食用の食べ物を買いに行く時間になった。行って、半額のシールがついたパンを見ると、買わないではいられない。毎日、毎日、同じことをやったりする。
そういうことで、自分のやることを同じことで埋めて行って、新しいことをやらない。
統合力がなくなっているので、新しいことをやると、次々に失敗してしまうのです。
しかし、そういう人でも、心の痛みがとれて安心してくると、統合力が戻ってくるんです。アスペルガー的じゃなくなってくるのです。もちろん、不安もだんだん減ってくる。
ということなんですよね。
この質問をした人は、いまも統合力が極端に落ちていると思います。
そうなると、うまく周囲を認識するとか、把握することができていないんですよね。
だから仕事とか、作業内容を説明されても、把握できていないんです。
たとえば、畑に竹で支柱を作るとします。支柱になる竹をスズランテープで結びつけて、といわれると、一生懸命にやるんです。
でも、狭い範囲しか見えなくなっています。同じ高さで揃えてと言っても、なかなか周りを見ても、高さがいいかどうかわかりません。
普通の認識力があれば、何となく高いなとか、何となく低いなってわかります。
「なんとなく」なんて言葉は、正に統合力があるところから出てくる言葉ですよね。
認識して考えて、低いんじゃないか、高いんじゃないかと判断する。で、このくらいの高さだったな、とわかる。それで結びつけます。
統合力を使わないと、なんかよくわからないけど、竹を結びつけることにだけ気持ちが向いて縛る。あ、そう言えば、高さ揃えろって言われた。改めて隣の高さを見る、それが間違っていてもかまわずに右へ倣えをする。
なんでもいいから、隣の人に揃えてしまう。気持ちがバラバラになって、どこを基準にしていたか忘れてしまう。みんな、そんなことやるものだから、まあいいか、となる。
それで、お父さんに怒られる。
怒っているわけじゃないけどね「何やっているんだよ」って言われてしまう。
一直線になるはずが、なっていなかったらがっかりするよね。
そういうことを次々にしてしまって、自分に対して信用をなくしているのです。だから、不安の先取りをしてしまう。きっと失敗するだろうと思ってしまうのでしょう。みんなの足引っ張っちゃうだろうなって。
逆に言うと、気持ちが回復してきて、心が整ってくると、周りが見えてきます。作業が的確にできるようになってきます。
作業をきちんとするのは、難しいですよ。勉強ができることと、その場に合わせて、一番適切な選択肢を選んで仕事をするということは、全然違うんですよね。
いま、さきこと、るりが帰ってきていますが、結構、仕事で苦しんだと思いますよ。
ここで回復して仕事に出る人はみなそうですが、るりは摂食障害で苦しい中で生きてきて、なのはなファミリーに来て、フルモデルチェンジしたるりとして働きに出て行ったんですね。
ニューモデルになって行ったはずなんですが、普通のおばさん、お姉さんが、こんなに能力高いのかってビックリしたはずです。
さきこも同じで、ここに来たときはレロレロだったけれど、元気に回復してから勤めに出て、普通の人は当たり前に、高いことを高いレベルでやるなとビックリしたはずです。
たとえば、建築関係や機械関係でも、高学歴で優秀な人が現場で優秀な仕事をできるかというと決してそうではない。頭がカチカチになっていると、壮大な仕事ばかり考えて、現場に合わせて融通のきく仕事がなかなかできない。学歴がない現場の叩き上げの人のほうがよほどいい仕事をすることはザラにあります。
かく言う僕も、カルチャーショックを何度も味わっています。小学校入学のときも、中学校行ったときも、大カルチャーショック。
高校で、自滅して、空中分解して、やり直そう、でたらめにやろう、エリートコースから外れようと、高校あたりから現実的な道を行こうとしました。
でも、苦しかった、東京に出てからも苦しかった。普通の人になれない。人間になりたい、と。
小学校1年のときから考えていました。
普通の人が簡単にできることができないのです。小学校1年生のとき、先生から君は海のほうの出身だから、社会で使う教材を作る手伝いをしてほしい、漁師が船に乗って、網で魚を捕っている絵を描いてほしいと言われた。
僕は数人の同級生と教室に残って、先生から頼まれた絵を描きました。
画材はクレヨンです。先生から指名があったわけなので、言われた通りにクレヨンで描いた。ところがクレヨンで、網の目を1本、1本描いていくと、網の目にならないんだね。クレヨンが太いから塗りつぶされてしまって網目にならない。
クレヨンじゃ無理だろうと思いながら塗り込んでいると、先生が、小野瀬君、何やっているんだって、来ました。何を描いているのだ、と。世の中難しいなと思いましたね。
小学校1年の時に、先生の期待に応えられなくて悪いなと思って、大きなカルチャーショックを味わいました。
真面目にやっているのが、なかなか結果に結びつかないショックです。
先生は、僕のクレヨンの上から鉛筆でかっかっかって線を描きましたね。網になりました。そういうことを経験する中で、少しずつ現実的な路線を獲得して行くんですね。
たぶん、さきこもそういう意味では世の中の難しさに苦しみながら慣れてきて、今はもう大丈夫と思う。
摂食障害の子がなのはなを卒業してから社会に出て味わう苦しみには、2つの苦しみがあると思います。
1つは、やっぱり、本当になのはな的な考えの人は少なくて、人を落としたり、享楽的な、今だけ良ければいいという生き方をしている人ばっかりだったり、やけくそで生きていたり、自分のことしか考えていない人が多い中で、自分だけ違う生き方を生きていくのは、孤独になりがちで、なかなか苦しい。そういう苦しさが1つです。
もう1つの苦しさは、簡単に言うと、仕事の質と量をどの程度でバランスすればいいのかっていうのが分かりにくいんです。
極めて高いレベルでやろうと思うと、時間がかかる。
摂食障害をしたことのない、苦しくない人は、何も悩まずに、ここって言うバランスをきちんと出せる。
そういう人は職場で先輩と意見が違ってもまったく頓着しません。こっちがいいとか、いやあっちのバランスって、2人で意見を言い合って、後腐れなくやれるんです。
ところが、摂食障害の人は、あんた何やっているのって言われたら、ビックリして、あわててそっちに合わせようとして、あたふたしちゃう。
そう言う大変さがあるんですよ。そうだよね。(さきこ あります)(るり すごいあります)
いま言った2つの苦しみは、そうそう、みんなも経験しているはずですよ。
小学校の頃、ここにいる人の7割は、真面目にやった人だと思います。
ところが「真面目にやってらあ」って馬鹿にされて、真面目じゃないフリ、勉強していないふりをしてきたと思います。同級生のいじめの対象になったら困るし、ということでかなり妥協して周囲に合わせてきているはずです。
先生の言う通りにしていたら「先生に媚びてらあ」って言われるので、素直じゃないふうに、見え方を軌道修正してきている。
外に出ても同じ。真面目にやろうとしても、変なこと言われるし、真面目じゃないやつが、的確に判断して、うまくやっているのを見ると、あんなふうにやらなくちゃいけないのかと、真面目だった自分の路線を大幅に変えたりしてきたはずです。
しかし、バランス悪くて、アップアップしていたら駄目だけれど、敢えて質の高いところで、私は真面目に生きますといって通す強さと、実力をつけるべきだと思います。
で、みんなを見ていると、すごく応用力がきかないですね。
中には、特定のことに対する実力が高いんです。勉強だったらできるでしょう。テキストの範囲内の問題ですから、それはできます。ただ、現実的には、世の中は応用問題ばかりです。
楽器もやりやすいですよね。演奏にはルールがありますし、練習したら誰でもできますからね。まずは、少なくとも、そういうことを確実に自分のものにして、それで自信をつけて、視野を広げて統合力をつけて、なおかつ高いレベルの仕事ができるようになったら、誰にも四の五の言わせないことができる。
不安の先取りをしてしまう人は、まったくそうなっていないのだと思います。
統合力がかなり落ちていて、認識できなくて、自分だけが間違ってしまったということがいっぱいあったり、周囲を待たせてばかりだと思うと、不安になります。
楽観的に前向きにいくのはいいけれど、急に統合力は上がりません。徐々にしか上がらない。
どんどん失敗していけばいいのです。なのはなファミリーは失敗していい場所です。ただ、失敗の仕方がありますから、上手に失敗してほしいんだね。失敗を隠すのは駄目です。失敗を明らかにしてほしい。自分にも、周りにも、私はこんな失敗をする人です、次からはこういう失敗はしないようにしよう、同じ失敗は2度としない、としていけばいいのです。
そう決めたら、失敗は少なくなっていって、少なくとも、ここでやっていることは、失敗しなくて済むようになる。
農業やったり、演奏をしたり、ダンスをしたり、ほかにもやることが幅広いですからね。そういうことが、ほぼ的確にできるようになったら、世の中に出ても、普通にやっている人にすぐに追いついて、それを超える仕事もできるようになって行きます。
みんな発展途上です。
ただし、発展途上の上にあぐらはかかないで、2度と同じような失敗はしない、そういう志を持って、いっぱい失敗しながら、同じ失敗を2度としないで伸びていく、そうしてほしいと思います。
作業の中でたくさん成功体験を積めば、作業が好きになり、楽しくなります。それを繰り返していくと、ああ明日が楽しみだな、と楽しみなことばかりになって、不安はなくなりますよ。
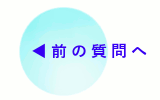


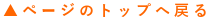

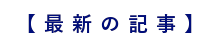
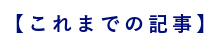
第1回~第100回(クリックすると一覧を表示します)
第1回「縦軸と横軸について」第2回「神様は何をしようとしているのか」
第3回「本で涙を流すことについて」
第4回「本を読んでも内容を忘れてしまうことについて」
第5回「時間をうまく使えるようになるには」
第6回「太宰治について」
第7回「摂食障害の人が片付けが苦手だったり、約束の時間に遅れてしまうのは何故ですか?」
第8回「自分のことを『僕』『おいら』と言うのをやめられなかったのは、なぜか」
第9回「おいしいカレーと、おいしくないカレーの違い」
第10回「楽しんで走る」
第11回「死ぬことへの考え」
第12回「『聞く』と『教えてもらう』」
第13回「頑張るフルマラソン」
第14回「他人の成功」
第15回「『今』という時間」
第16回「不安の先取り」
第17回「良い協力関係」
第18回「急に悲しくなる」
第19回「夢の持ち方について」
第20回「心の許容範囲」
第21回「疲れるのが怖い」
第22回「スポーツの勝ち負け」
第23回「人といること」
第24回「“好き”という気持ち」
第25回「何でも知っている」
第26回「舞台鑑賞が怖かったこと」
第27回「生まれ変わるとしたら」
第28回「一番感動した景色、美しい国はどこですか?」
第29回「好きな時代はいつですか」
第30回「体型について」
第31回「行きたいところ」
第32回「悲しくなったら、動く」
第33回「意志を持てないこと」
第34回「心を動かす」
第35回「恋愛できますか」
第36回「日記の重要性」
第37回「心配されたい」
第38回「ONとOFF」
第39回「いつも同じ態度で」
第40回「涙腺が弱い」
第41回「子供が苦手」
第42回「正しいことを通そうとして」
第43回「流されて生きる」
第44回「才能について」
第45回「身長は伸びますか」
第46回「否定感が強い」
第47回「ぐっすり眠れない」
第48回「見え方、感じ方」
第49回「強さについて」
第50回「自分の出し方」
第51回「身体の調子と気持ち」
第52回「何のために変わるか」
第53回「痛みを知る」
第54回「投げやりな気持ち」
第55回「未完成」
第56回「相手を許す」
第57回「書けないとき」
第58回「甘いと甘え」
第59回「イライラしない」
第60回「落ち込んだ時」
第61回「生きているなら」
第62回「わからない問題は」
第63回「眠ること」
第64回「子育てについて」
第65回「夫婦で大切なこと」
第66回「自己否定について」
第67回「友達が欲しい人、そうでない人」
第68回「未来を信じる」
第69回「山を登ると」
第70回「リーダーをすると苦しくさせる」
第71回「自分から人を好きになる」
第72回「小さいころからの恐怖心」
第73回「お姉さんのような存在を」
第74回「作業に対して気持ちの落差が激しい」
第75回「大きな希望を持つとき①」
第76回「大きな希望を持つとき②」
第77回「夢について・集中力について」
第78回「やるべきことをできていなくて苦しい」
第79回「やるべきことをできていなくて苦しい②」
第80回「真面目さは何のために」
第81回「高いプライドをつくるには」
第82回「番外編:そうだ、お母さんにきいてみよう!」
第83回「相談、確認が多いことについて」
第84回「自信を持つ」
第85回「間の良さ、間の悪さ」
第86回「過去を美化してしまう」
第87回「統合力を高めるには」
第88回「見張られているような不安」
第89回「どうして人間だけに気持ちが必要なのか」
第90回「休日になるとやる気がなくなってしまう」
第91回「低気圧」
第92回「どうして動物を飼うの?」
第93回「自分を褒める話をするには」
第94回「眠れない」
第95回「ふいに恥ずかしくなる」
第96回「躾について」
第97回「壁をなくしてオープンになるには」
第98回「自分がオーラのある人になるには」
第99回「私のストレスは何?」
第100回「社会性を身につける」
第101回~第150回(クリックすると一覧を表示します)
第101回「依存を切り離す期間は? その後はどう変わる?」
第102回「依存を切り離すことについて②」
第103回「会話が理解できない・生きる意味」
第104回「何者にもなれないのでは、という不安」
第105回「一緒に長時間いられない」
第106回「人の気持ちを汲めない」
第107回「リーダーとしてちゃんと動くには」
第108回「仕事への情熱と、興味があること」
第109回「日々の習慣を持つ」
第110回「自分のアスペルガー的な要素について」
第111回「外見について」
第112回「芸術、情緒、愛情 心の深さ」
第113回「なぜ風俗業は禁止にされないのか」
第114回「生き難さを抱えていなかったら、どんな将来の夢を」
第115回「健全な家庭なら自我は育つのか」
第116回「自我を育てる」
第117回「説明が理解できない」
第118回「好きな花①」
第119回「好きな花②」
第120回「血を連想させる単語を聞くと」
第121回「社会性と、基本的な姿勢」
第122回「深い関係をとって生きる」
第123回「ノルマ感、義務感が強い」
第124回「野菜の収穫基準がわからなくなる」
第125回「自分を楽しませること、幸せに過ごさせることが難しい」
第126回「向上心を持てないこと」
第127回「アーティスティックな心」
第128回「野性味を取り戻す」
第129回「個人プレイからチームプレイへ」
第130回「すべてのことを高いレベルでやりたい」
第131回「なぜ、痩せているほうが良いと思われるのですか?」
第132回「予定が変わると、気持ちがもやもやする」
第133回「楽観主義者と悲観主義者の境界線」
第134回「上品に、笑顔で、美しく」
第135回「続『上品に、笑顔で、美しく』」
第136回「嘘をつけない」
第137回「お父さんが怖い 前編」
第138回「お父さんが怖い 後編」
第139回「見事やで」
第140回「頼まれごとが不安・時間に遅れる①」
第141回「頼まれごとが不安・時間に遅れる②」
第142回「頼まれごとが不安・時間に遅れる③」
第143回「大きな声を出すこと」
第144回「時間の使い方」
第145回「お腹がすく」
第146回「本を読む時、第三者の視点になってしまう」
第147回「罰ゲームの答えとユーモア」
第148回「アイデアが出ないこと」
第149回「気持ちと身体の助走」
第150回「花や動物を可愛いと思えない」
第151回~第200回(クリックすると一覧を表示します)
第151回「美味しいセロリ」
第152回「尊敬している人といると、あがってしまう」
第153回「考え事がやめられない」
第154回「認めてもらいたい気持ち」
第155回「寝汗をかかなくなった」
第156回「時間の不安について」
第157回「楽器を練習したい、本を読みたい」
第158回「疲れを認めたくない」
第159回「アトピーと蕁麻疹」
第160回「はっきりした人になりたい」
第161回「会話と、興味の深さについて」
第162回「思春期の不安定」
第163回「潔癖症について」
第164回「自尊心」
第165回「自分の身体のサイズ感をとらえるのが苦手」
第166回「兄弟を心配する気持ち」
第167回「自分の声への違和感」
第168回「野菜の調子が悪いと、自己否定してしまう」
第169回「好きな気持ちと、誤解をされることへの不安について」
第170回「トイレが近いことについて」
第171回「競争意識について①」
第172回「競争意識について②」
第173回「コンディションによって態度が変わる人、変わらない人」
第174回「恐がりなことについて」
第175回「テンション」
第176回「目を見ること、見られること」
第177回「よいお母さんになる10か条」
第178回「音楽と我欲①」
第179回「音楽と我欲②」
第180回「時間の使い方と焦りの気持ち」
第181回「自分に疑心暗鬼になって、不安に陥ってしまうのはなぜ」
第182回「有志の募集に手を挙げづらい」
第183回「緻密に」
第184回「いつも怖い」
第185回「体型に対するこだわり」
第186回「気持ちの切り替えが、うまくできない」
第187回「米ぬかぼかし作り」
第188回「評価すること」
第189回「堂々とした人に怯えてしまう ①」
第190回「堂々とした人に怯えてしまう ②」
第191回「耳が良くないこと」
第192回「限界」
第193回「物を簡単に捨てることができてしまう」
第194回「整理整頓、片付けができない」
第195回「次のミーティングは、いつですか?」
第196回「整理が過ぎるのは症状ですか」
第197回「人をもっと理解したいということについて」
第198回「体育の授業が怖くて、さぼっていたことについて」
第199回「完璧が怖い」
第200回「やるべきことに追われてしまいがちな気持ちについて」
第201回~第250回(クリックすると一覧を表示します)
第201回「正面から受け取りすぎることについて」
第202回「手持ち無沙汰にさせることが怖い」
第203回「生き物が好きで触りたくなる気持ちについて」
第204回「魚の食べ方について」
第205回「ステージで間違いがあったときは」
第206回「作業で焦ってしまう」
第207回「調理されて食べられる魚はかわいそう?」
第208回「頑張ろうとすることに疲れた」
第209回「自己愛性パーソナリティ」
第210回「期待について その①」
第211回「期待について その②」
第212回「アウトプットで生きる」
第213回「キャパシティを大きくしたい」
第214回「コミュニケーション」
第215回「秋が寂しい」
第216回「我欲と、自分を大切にすることの違い」
第217回「声を前に出して歌うには」
第218回「できる気がしない、と感じてしまう」
第219回「苦手なことをしている時間を苦痛に感じてしまう」
第220回「握力について」
第221回「喜び合うための全力」
第222回「リモコンの操作と、ゴミの分別が覚えられなかったこと」
第223回「相談をしたり、買ってもらったりすることが怖い」
第224回「ケアレスミスが多い」
第225回「恥ずかしさにどう対処するか」
第226回「きつく締められないこと」
第227回「豆掴みと羽根つきが、うまくできるようになっていた」
第228回「プライドを守り合える関係」
第229回「人間味を学ぶために」
第230回「リーダーをするときの不安と罪悪感」
第231回「幸せについて」
第232回「不思議ちゃんと言われていたのはなぜか」
第233回「話の絶えない人になるには」
第234回「サービスをする人になる」
第235回「ソフトボール部に入らなくてはいけない気がする」
第236回「ディストピアと野蛮人の村」
第237回「好きと言ってみる」
第238回「質問がまとまらない」
第239回「ソフトクリーム」
第240回「謙虚について」
第241回「人との間にしか幸せはないこと」
第242回「思いっ切り遊んだことがない」
第243回「癇癪について」
第244回「友達について その①」
第245回「友達について その②」
第246回「センスよく生きる」
第247回「根拠のない自信」
第248回「先生になること」
第249回「演じること、正直になること」
第250回「怒りと感謝の気持ちは共存しない」
第251回~第300回(クリックすると一覧を表示します)
第251回「アメリカンドリーム」
第252回「悲しむこと」
第253回「限界までやってみる」
第254回「リーダーの向き不向きについて」
第255回「悲しくならない求め方」
第256回「人前に立つ緊張」
第257回「野菜の見方」
第258回「プライバシーについて」
第259回「寝相について(前半)」
第260回「寝相について(後半)」
第261回「変わっていくことについていけない恐ろしさ」
第262回「速く書く事」
第263回「利他心について」
第264回「集中力について」
第265回「読書について 解釈と鑑賞」
第266回「年齢、役割に見合った振る舞いについて」
第267回「相手に喜んでもらいたい気持ちと、自分が幸せを感じることの怖さ」
第268回「相手を幸せにするということについて」
第269回「シンプルであること」
第270回「人のために動くとき」
第271回「周囲の人や家族のなかで浮いている感覚があったことと、個性について」
第272回「楽しませる人、発信する人になりたい」
第273回「目の前のことに集中できない・利他心と利己心について」
第274回「仕事への心配と、自分が空っぽの人間だと感じることについて」
第275回「理解されたいという欲求が強かったこと」
第276回「人前でのびのびと感情表現出来るようになるには、どうすればよいか」
第277回「筋肉をつかって疲れると、悲しくなってしまうこと」
第278回「深い信頼関係は、どう築いていったらいいのか」
第279回「ダークマターの存在に守られていること」
第280回「利他心の球技について」
第281回「小さな楽しみ、食器洗いについて」
第282回「どんなリーダーを目指したらいいか」
第283回「小さい子どもの遊ばせ方について」
第284回「大人と子どもの境界線について」
第285回「経済観念について」
第286回「自分に変に自信があること」
第287回「泣けるようになったこと」
第288回「味覚が変わったこと」
第289回「ここぞというときに失敗してしまうこと」
第290回「親を否定できなかった理由」
第291回「自分が何に傷ついたのかわかりにくい」
第292回「聞いたことを言葉でまとめるのが苦手」
第293回「リーダーをすることへの罪悪感」
第294回「子供の頃に虐められやすかったこと」
第295回「新たな価値観を作ること」
第296回「捕食するのを見るのが好き」
第297回「身体の調子を安定させるにはどうすればいいのか」
第298回「みんなと達成感を味わえるリーダーになるには?」
第299回「『老人と海』を読んでどう感じたらよいのか」
第300回「毎日同じものを食べても飽きないのはどうしてか」
第301回~第350回(クリックすると一覧を表示します)
第301回「国民年金について」
第302回「サプリメントの必要」
第303回「自動車の運転について(車の運転で大事なこと)」
第304回「具体的に考えること」
第305回「関係の取り方」
第306回「自分の行動でおかしいと思うこと3つ」
第307回「イライラしてきつい空気を出してしまう」
第308回「やらなければいけないと感じて苦しくなるのはなぜか」
第309回「年齢と自覚が噛み合わないこと」
第310回「歌声のピッチが合うこと」
第311回「眠気がなくなったこと」
第312回「湯舟でおしっこをしていたのはなぜ?」
第313回「カッコイイ男性に対して引いてしまうのはどうしてか」
第314回「上手な緊張感の持ち方」
第315回「リーダーをするときに不安があったり優柔不断になること」
第316回「目立つことを避けてしまうのはどうしてですか」
第317回「2人で作業リーダーをするのが苦手」
第318回「ウクライナの戦争など大変な状況が起きているとき、その場に自分がいないことを申し訳なく思うこと」
第319回「講演会で話す時の秘訣」
第320回「吹き矢がうまくいく時とうまくいかない時があること」
第321回「ハングリー精神と、幸せのその日暮らしの両立について」
第322回「小学生みたいな日記になってしまう」
第323回「誰のために能動的か」
第324回「頭を使う人、使わない人」
第325回「セブンブリッジの楽しみ方」
第326回「罰ゲームをするときに恥ずかしくて困ってしまう」
第327回「これから社会人になるにあたって気を付けるべきこと」
第328回「親が子供に対する本当の優しさとは」
第329回「頭を使えば作業のスピードは上がりますか」
第330回「人前でうまく話すことができない」
第331回「報告や相談が苦手」
第332回「プレゼンテーションで緊張することについて」
第333回「作業でうまく空気を作れない」
第334回「急なスケジュール変更を受け入れられること」
第335回「本の内容が入ってこない」
第336回「あるべきイメージをどうしたら持てるのか」
第337回「表現しなければならないという気持ちが強かったこと」
第338回「養護施設で人の生き方を教えることについて」
第339回「自分の評価をぶらさずに肯定感を保つには」
第340回「いいサブリーダーとは」
第341回「自分のマイナスを捉えることが苦手」
第342回「すぐに涙が出るのは自分が薄っぺらいからですか」
第343回「摂食障害から回復した状態とは」
第344回「楽なほうに逃げてしまう自分は、まず何を変えればいいか」
第345回「体重が増えると大きな気持ちでいられるようになった」
第346回「気持ちに強弱をつけるということ」
第347回「自分を縛りがち」
第348回「相談するのが苦手」
第349回「敬語でなく横並びの関係を取りたい」
第350回「内向的に育った自分の欠落をどう捉えたらいいか」
第351回~第400回(クリックすると一覧を表示します)
第351回「『なんで』という言葉が多い子供とそうでない子供の違い」
第352回「コンタクトレンズを入れていると頭が痛くなる」
第353回「怒られないための人生を変えるために、まずどうすればよいか」
第354回「啓発本に逃げるような読み方にならないためには」
第355回「どうすればいいリーダーとしての話し方ができるのか」
第356回「自分が薄っぺらいのを直していくにはどうしたらいいか」
第357回「自信を常に安定して持つにはどうすればいいか」
第358回「話すことで気持ちがチャージされる」
第359回「ナルシストと自信がない人」
第360回「朗読をするようになってからビクビクするのが減った」
第361回「大きな目標は、いつ持つものなのですか」
第362回「踏み込まれる怖さ」
第363回「人と人との間に境界線を持つこと」
第364回「怒られやすいタイプ」
第365回「宗教心とモラルについて」
第366回「生育環境が自分より豊かな人に対して壁を作ってしまったり、豊かでなかったことの寂しさや負の気持ちはどうしたらとれるのか」
第367回「桃の味が古い樹と若い木で違うのは」
第368回「自傷について」
第369回「適切な兄妹関係とは」
第370回「野菜を上手に育てられていない心持を具体的にどう直したらよいか」
第371回「甘えをなくし続けることが自分にとって回復し続けることですか」
第372回「AIについて」
第373回「話を要約するのが苦手」
第374回「要領がいい人と、要領が悪い人の差」
第375回「自信の具体的なつけかた」
第376回「物を壊す頻度が多く、どうしたらなくせるか」
第377回「0か100思考をどうしたら克服できるか」
第378回「本を読むとき、作者が伝えたいことが読み取れない」
第379回「シスターの人とどう作業をするか」
第380回「朗読をするとき、面白い場面でも笑わずに読むにはどうすればよいか」
第381回「いつもと違う真剣な空気を怖いと感じてしまう」
第382回「人や野菜の気持ちが汲めないことが多い」
第383回「人をどう評価するか」
第384回「自閉症や発達障害が増えているのはなぜなのか」
第385回「いじられキャラになってしまうのはなぜか」
第386回「小説から現実の世界に戻れないのはおかしいことか」
第387回「ミスをするのが怖い気持ち」
第388回「人と話をするようにどれくらい努めるべきか」
第389回「人との距離感について」
第390回「普通の人になりたいと思うほど、苦しくなったのはなぜ?」
第391回「運転中、後ろから 車に追突されそうなときは」
第392回「窓口で会う、素敵な人のようになりたい」
第393回「人と話すときに遠慮したり、混乱したりして、何も言えなくなってしまう」
第394回「日本の縫製業のこれからについて」
第395回「地で生きていることについて」
第396回「人に言葉を伝えるのが下手だと思う」
第397回「自分に合う服」
第398回「人と目を合わせるのが怖い」
第399回「謙虚な気持ちとは」
第400回「気遣いができるようになるには」
第401回~(クリックすると一覧を表示します)
第401回「写真と自分のイメージがかけ離れている」
第402回「地で生きていると苦しくなること」
第403回「急かされている感じがして焦ってしまう」
第404回「相手の本質がわかるようになるにはどうしたらいいか」
第405回「怒りについて」
第406回「神様を信じる気持ちについて」
第407回「未熟な自分を受け入れることについて」
Copyright © なのはなファミリー 2024 | WordPress Theme by MH Themes