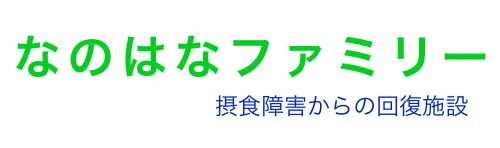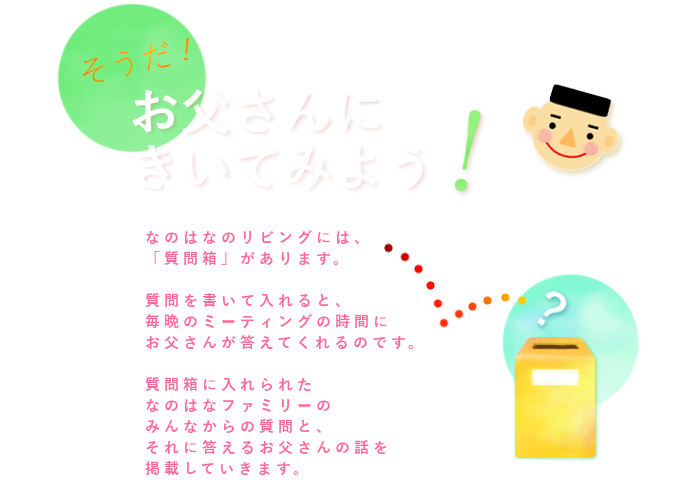
第224回「ケアレスミスが多い」
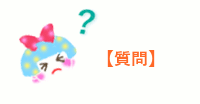
ケアレスミスについて
私は問題を解いていて、ケアレスミスをすることが多いと思いました。桁を間違える、足す引くを逆にしている、空欄を見落としている、など、答え合わせをすると「どうして」と言いたくなるような間違いがあります。6,7問に1回くらいやってしまいます。
こういうミスは小学5年生のときに突然するようになって、それからミスをするのが普通になってしまっていたのですが、これはおかしい、治すべきことなのではないかと思いました。
なぜこんなミスをしてしまうのか、どうしたら治るのか、教えていただけると嬉しいです。
自分の答え
間違ってはいけないというプレッシャーが無意識にあって、それに頭が囚われている部分があるから。そのプレッシャーがなくなれば治る。
補足
小学5年生は生理が来た年であり、祖母の体調が悪くなり、母が仕事をやめた年で、私が強迫性障害の症状を強く出していた年です。
【お父さんの答え】
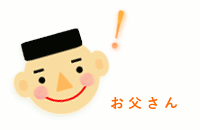
小学5年生から、直らないんですね。
ケアレスミスをするようになってから、ケアレスミスをするパターンまで頭に定着してしまっている、そんなふうに思いますね。
なんていうかな、ケアレスミスというのはある種、頭が麻痺状態になっているんですよね。ちょっと考えてみると、人って、緊張状態にあったり、新しい物事に対しているときは結構、集中度が高いんですけど、慣れてくると集中度がガクンと落ちる。
だから人工的に、新しい環境をつくるというか、自分をだますというか、そんなふうにするといいでしょうね。
例えば問題を上から順にやっていく、すると6、7問目には慣れてきて必ずケアレスミスをやりますよ。そこで、あえて非常事態に自分を追い込む。1,2をやったら3,4を飛ばして最後の問題をやってみる、それから、飛行機がなんで飛ぶのか考えてみるとか、船はなぜ沈まないのか、プロペラにどういう曲がりをつけたら効率のいいプロペラかと考えてみる。考えてもわからないから……わからないな、となってから次の問題へと進む。すると目の前の問題が、簡単に見えてくる。
自分の頭を騙す、新鮮にしておく、そういうことを人工的にやってはどうでしょうかね。
これってイギリス人だったらユーモアだったりするんですね。普通の人でも、なぞなぞやってたら楽しいでしょ。下らないなぞなぞが、面白い。なぞなぞをみんなでやりながらする畑仕事は効率いいですよ。
人間の頭って一つのことだけやっていると眠くなっていく。だれて、嫌になっていく。
集中力の強い人ほど、1つのことをやっていくのが嫌になっていきますよ。集中力がだんだん落ちていき、嫌になるというのはわかりきっているんですから、2つか3つの仕事を同時にやるといいです。
方法によっては1問目の問題を途中まで読んだら2問目の問題を途中まで読んで、3問目を読んだら1問目に戻って。絶対混乱しますけど、混乱しないようにしてケアレスミスしないように緊張しながらやるとミスしない。つじつま合わせるのに大変になってきますけどね。
僕も、書かないといけない書き物が、なかなか終わっていないんですよ。書けない、書くの嫌だな億劫だなと思っちゃう。
それが花のキャプションを書く、お父さんにきいてみようを書くって3つ同時に書き始めたら割とスッスッといく。
そういうふうに、頭をわざととっ散らかすというか、そういうふうにイレギュラーな状態にもっていくのがケアレスミスをしないコツなんじゃないか、と思います。人と話しているときでも、全然、別の発想を時々織り交ぜながら話していくと、話しが常に新鮮で、人との関係もスムーズになりやすいです。ということで、自分に変化をつけていきましょう、というのが答えです。
(2019年12月20日掲載)
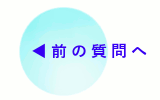


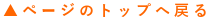

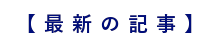
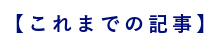
第1回~第100回(クリックすると一覧を表示します)
第1回「縦軸と横軸について」第2回「神様は何をしようとしているのか」
第3回「本で涙を流すことについて」
第4回「本を読んでも内容を忘れてしまうことについて」
第5回「時間をうまく使えるようになるには」
第6回「太宰治について」
第7回「摂食障害の人が片付けが苦手だったり、約束の時間に遅れてしまうのは何故ですか?」
第8回「自分のことを『僕』『おいら』と言うのをやめられなかったのは、なぜか」
第9回「おいしいカレーと、おいしくないカレーの違い」
第10回「楽しんで走る」
第11回「死ぬことへの考え」
第12回「『聞く』と『教えてもらう』」
第13回「頑張るフルマラソン」
第14回「他人の成功」
第15回「『今』という時間」
第16回「不安の先取り」
第17回「良い協力関係」
第18回「急に悲しくなる」
第19回「夢の持ち方について」
第20回「心の許容範囲」
第21回「疲れるのが怖い」
第22回「スポーツの勝ち負け」
第23回「人といること」
第24回「“好き”という気持ち」
第25回「何でも知っている」
第26回「舞台鑑賞が怖かったこと」
第27回「生まれ変わるとしたら」
第28回「一番感動した景色、美しい国はどこですか?」
第29回「好きな時代はいつですか」
第30回「体型について」
第31回「行きたいところ」
第32回「悲しくなったら、動く」
第33回「意志を持てないこと」
第34回「心を動かす」
第35回「恋愛できますか」
第36回「日記の重要性」
第37回「心配されたい」
第38回「ONとOFF」
第39回「いつも同じ態度で」
第40回「涙腺が弱い」
第41回「子供が苦手」
第42回「正しいことを通そうとして」
第43回「流されて生きる」
第44回「才能について」
第45回「身長は伸びますか」
第46回「否定感が強い」
第47回「ぐっすり眠れない」
第48回「見え方、感じ方」
第49回「強さについて」
第50回「自分の出し方」
第51回「身体の調子と気持ち」
第52回「何のために変わるか」
第53回「痛みを知る」
第54回「投げやりな気持ち」
第55回「未完成」
第56回「相手を許す」
第57回「書けないとき」
第58回「甘いと甘え」
第59回「イライラしない」
第60回「落ち込んだ時」
第61回「生きているなら」
第62回「わからない問題は」
第63回「眠ること」
第64回「子育てについて」
第65回「夫婦で大切なこと」
第66回「自己否定について」
第67回「友達が欲しい人、そうでない人」
第68回「未来を信じる」
第69回「山を登ると」
第70回「リーダーをすると苦しくさせる」
第71回「自分から人を好きになる」
第72回「小さいころからの恐怖心」
第73回「お姉さんのような存在を」
第74回「作業に対して気持ちの落差が激しい」
第75回「大きな希望を持つとき①」
第76回「大きな希望を持つとき②」
第77回「夢について・集中力について」
第78回「やるべきことをできていなくて苦しい」
第79回「やるべきことをできていなくて苦しい②」
第80回「真面目さは何のために」
第81回「高いプライドをつくるには」
第82回「番外編:そうだ、お母さんにきいてみよう!」
第83回「相談、確認が多いことについて」
第84回「自信を持つ」
第85回「間の良さ、間の悪さ」
第86回「過去を美化してしまう」
第87回「統合力を高めるには」
第88回「見張られているような不安」
第89回「どうして人間だけに気持ちが必要なのか」
第90回「休日になるとやる気がなくなってしまう」
第91回「低気圧」
第92回「どうして動物を飼うの?」
第93回「自分を褒める話をするには」
第94回「眠れない」
第95回「ふいに恥ずかしくなる」
第96回「躾について」
第97回「壁をなくしてオープンになるには」
第98回「自分がオーラのある人になるには」
第99回「私のストレスは何?」
第100回「社会性を身につける」
第101回~第150回(クリックすると一覧を表示します)
第101回「依存を切り離す期間は? その後はどう変わる?」
第102回「依存を切り離すことについて②」
第103回「会話が理解できない・生きる意味」
第104回「何者にもなれないのでは、という不安」
第105回「一緒に長時間いられない」
第106回「人の気持ちを汲めない」
第107回「リーダーとしてちゃんと動くには」
第108回「仕事への情熱と、興味があること」
第109回「日々の習慣を持つ」
第110回「自分のアスペルガー的な要素について」
第111回「外見について」
第112回「芸術、情緒、愛情 心の深さ」
第113回「なぜ風俗業は禁止にされないのか」
第114回「生き難さを抱えていなかったら、どんな将来の夢を」
第115回「健全な家庭なら自我は育つのか」
第116回「自我を育てる」
第117回「説明が理解できない」
第118回「好きな花①」
第119回「好きな花②」
第120回「血を連想させる単語を聞くと」
第121回「社会性と、基本的な姿勢」
第122回「深い関係をとって生きる」
第123回「ノルマ感、義務感が強い」
第124回「野菜の収穫基準がわからなくなる」
第125回「自分を楽しませること、幸せに過ごさせることが難しい」
第126回「向上心を持てないこと」
第127回「アーティスティックな心」
第128回「野性味を取り戻す」
第129回「個人プレイからチームプレイへ」
第130回「すべてのことを高いレベルでやりたい」
第131回「なぜ、痩せているほうが良いと思われるのですか?」
第132回「予定が変わると、気持ちがもやもやする」
第133回「楽観主義者と悲観主義者の境界線」
第134回「上品に、笑顔で、美しく」
第135回「続『上品に、笑顔で、美しく』」
第136回「嘘をつけない」
第137回「お父さんが怖い 前編」
第138回「お父さんが怖い 後編」
第139回「見事やで」
第140回「頼まれごとが不安・時間に遅れる①」
第141回「頼まれごとが不安・時間に遅れる②」
第142回「頼まれごとが不安・時間に遅れる③」
第143回「大きな声を出すこと」
第144回「時間の使い方」
第145回「お腹がすく」
第146回「本を読む時、第三者の視点になってしまう」
第147回「罰ゲームの答えとユーモア」
第148回「アイデアが出ないこと」
第149回「気持ちと身体の助走」
第150回「花や動物を可愛いと思えない」
第151回~第200回(クリックすると一覧を表示します)
第151回「美味しいセロリ」
第152回「尊敬している人といると、あがってしまう」
第153回「考え事がやめられない」
第154回「認めてもらいたい気持ち」
第155回「寝汗をかかなくなった」
第156回「時間の不安について」
第157回「楽器を練習したい、本を読みたい」
第158回「疲れを認めたくない」
第159回「アトピーと蕁麻疹」
第160回「はっきりした人になりたい」
第161回「会話と、興味の深さについて」
第162回「思春期の不安定」
第163回「潔癖症について」
第164回「自尊心」
第165回「自分の身体のサイズ感をとらえるのが苦手」
第166回「兄弟を心配する気持ち」
第167回「自分の声への違和感」
第168回「野菜の調子が悪いと、自己否定してしまう」
第169回「好きな気持ちと、誤解をされることへの不安について」
第170回「トイレが近いことについて」
第171回「競争意識について①」
第172回「競争意識について②」
第173回「コンディションによって態度が変わる人、変わらない人」
第174回「恐がりなことについて」
第175回「テンション」
第176回「目を見ること、見られること」
第177回「よいお母さんになる10か条」
第178回「音楽と我欲①」
第179回「音楽と我欲②」
第180回「時間の使い方と焦りの気持ち」
第181回「自分に疑心暗鬼になって、不安に陥ってしまうのはなぜ」
第182回「有志の募集に手を挙げづらい」
第183回「緻密に」
第184回「いつも怖い」
第185回「体型に対するこだわり」
第186回「気持ちの切り替えが、うまくできない」
第187回「米ぬかぼかし作り」
第188回「評価すること」
第189回「堂々とした人に怯えてしまう ①」
第190回「堂々とした人に怯えてしまう ②」
第191回「耳が良くないこと」
第192回「限界」
第193回「物を簡単に捨てることができてしまう」
第194回「整理整頓、片付けができない」
第195回「次のミーティングは、いつですか?」
第196回「整理が過ぎるのは症状ですか」
第197回「人をもっと理解したいということについて」
第198回「体育の授業が怖くて、さぼっていたことについて」
第199回「完璧が怖い」
第200回「やるべきことに追われてしまいがちな気持ちについて」
第201回~第250回(クリックすると一覧を表示します)
第201回「正面から受け取りすぎることについて」
第202回「手持ち無沙汰にさせることが怖い」
第203回「生き物が好きで触りたくなる気持ちについて」
第204回「魚の食べ方について」
第205回「ステージで間違いがあったときは」
第206回「作業で焦ってしまう」
第207回「調理されて食べられる魚はかわいそう?」
第208回「頑張ろうとすることに疲れた」
第209回「自己愛性パーソナリティ」
第210回「期待について その①」
第211回「期待について その②」
第212回「アウトプットで生きる」
第213回「キャパシティを大きくしたい」
第214回「コミュニケーション」
第215回「秋が寂しい」
第216回「我欲と、自分を大切にすることの違い」
第217回「声を前に出して歌うには」
第218回「できる気がしない、と感じてしまう」
第219回「苦手なことをしている時間を苦痛に感じてしまう」
第220回「握力について」
第221回「喜び合うための全力」
第222回「リモコンの操作と、ゴミの分別が覚えられなかったこと」
第223回「相談をしたり、買ってもらったりすることが怖い」
第224回「ケアレスミスが多い」
第225回「恥ずかしさにどう対処するか」
第226回「きつく締められないこと」
第227回「豆掴みと羽根つきが、うまくできるようになっていた」
第228回「プライドを守り合える関係」
第229回「人間味を学ぶために」
第230回「リーダーをするときの不安と罪悪感」
第231回「幸せについて」
第232回「不思議ちゃんと言われていたのはなぜか」
第233回「話の絶えない人になるには」
第234回「サービスをする人になる」
第235回「ソフトボール部に入らなくてはいけない気がする」
第236回「ディストピアと野蛮人の村」
第237回「好きと言ってみる」
第238回「質問がまとまらない」
第239回「ソフトクリーム」
第240回「謙虚について」
第241回「人との間にしか幸せはないこと」
第242回「思いっ切り遊んだことがない」
第243回「癇癪について」
第244回「友達について その①」
第245回「友達について その②」
第246回「センスよく生きる」
第247回「根拠のない自信」
第248回「先生になること」
第249回「演じること、正直になること」
第250回「怒りと感謝の気持ちは共存しない」
第251回~第300回(クリックすると一覧を表示します)
第251回「アメリカンドリーム」
第252回「悲しむこと」
第253回「限界までやってみる」
第254回「リーダーの向き不向きについて」
第255回「悲しくならない求め方」
第256回「人前に立つ緊張」
第257回「野菜の見方」
第258回「プライバシーについて」
第259回「寝相について(前半)」
第260回「寝相について(後半)」
第261回「変わっていくことについていけない恐ろしさ」
第262回「速く書く事」
第263回「利他心について」
第264回「集中力について」
第265回「読書について 解釈と鑑賞」
第266回「年齢、役割に見合った振る舞いについて」
第267回「相手に喜んでもらいたい気持ちと、自分が幸せを感じることの怖さ」
第268回「相手を幸せにするということについて」
第269回「シンプルであること」
第270回「人のために動くとき」
第271回「周囲の人や家族のなかで浮いている感覚があったことと、個性について」
第272回「楽しませる人、発信する人になりたい」
第273回「目の前のことに集中できない・利他心と利己心について」
第274回「仕事への心配と、自分が空っぽの人間だと感じることについて」
第275回「理解されたいという欲求が強かったこと」
第276回「人前でのびのびと感情表現出来るようになるには、どうすればよいか」
第277回「筋肉をつかって疲れると、悲しくなってしまうこと」
第278回「深い信頼関係は、どう築いていったらいいのか」
第279回「ダークマターの存在に守られていること」
第280回「利他心の球技について」
第281回「小さな楽しみ、食器洗いについて」
第282回「どんなリーダーを目指したらいいか」
第283回「小さい子どもの遊ばせ方について」
第284回「大人と子どもの境界線について」
第285回「経済観念について」
第286回「自分に変に自信があること」
第287回「泣けるようになったこと」
第288回「味覚が変わったこと」
第289回「ここぞというときに失敗してしまうこと」
第290回「親を否定できなかった理由」
第291回「自分が何に傷ついたのかわかりにくい」
第292回「聞いたことを言葉でまとめるのが苦手」
第293回「リーダーをすることへの罪悪感」
第294回「子供の頃に虐められやすかったこと」
第295回「新たな価値観を作ること」
第296回「捕食するのを見るのが好き」
第297回「身体の調子を安定させるにはどうすればいいのか」
第298回「みんなと達成感を味わえるリーダーになるには?」
第299回「『老人と海』を読んでどう感じたらよいのか」
第300回「毎日同じものを食べても飽きないのはどうしてか」
第301回~第350回(クリックすると一覧を表示します)
第301回「国民年金について」
第302回「サプリメントの必要」
第303回「自動車の運転について(車の運転で大事なこと)」
第304回「具体的に考えること」
第305回「関係の取り方」
第306回「自分の行動でおかしいと思うこと3つ」
第307回「イライラしてきつい空気を出してしまう」
第308回「やらなければいけないと感じて苦しくなるのはなぜか」
第309回「年齢と自覚が噛み合わないこと」
第310回「歌声のピッチが合うこと」
第311回「眠気がなくなったこと」
第312回「湯舟でおしっこをしていたのはなぜ?」
第313回「カッコイイ男性に対して引いてしまうのはどうしてか」
第314回「上手な緊張感の持ち方」
第315回「リーダーをするときに不安があったり優柔不断になること」
第316回「目立つことを避けてしまうのはどうしてですか」
第317回「2人で作業リーダーをするのが苦手」
第318回「ウクライナの戦争など大変な状況が起きているとき、その場に自分がいないことを申し訳なく思うこと」
第319回「講演会で話す時の秘訣」
第320回「吹き矢がうまくいく時とうまくいかない時があること」
第321回「ハングリー精神と、幸せのその日暮らしの両立について」
第322回「小学生みたいな日記になってしまう」
第323回「誰のために能動的か」
第324回「頭を使う人、使わない人」
第325回「セブンブリッジの楽しみ方」
第326回「罰ゲームをするときに恥ずかしくて困ってしまう」
第327回「これから社会人になるにあたって気を付けるべきこと」
第328回「親が子供に対する本当の優しさとは」
第329回「頭を使えば作業のスピードは上がりますか」
第330回「人前でうまく話すことができない」
第331回「報告や相談が苦手」
第332回「プレゼンテーションで緊張することについて」
第333回「作業でうまく空気を作れない」
第334回「急なスケジュール変更を受け入れられること」
第335回「本の内容が入ってこない」
第336回「あるべきイメージをどうしたら持てるのか」
第337回「表現しなければならないという気持ちが強かったこと」
第338回「養護施設で人の生き方を教えることについて」
第339回「自分の評価をぶらさずに肯定感を保つには」
第340回「いいサブリーダーとは」
第341回「自分のマイナスを捉えることが苦手」
第342回「すぐに涙が出るのは自分が薄っぺらいからですか」
第343回「摂食障害から回復した状態とは」
第344回「楽なほうに逃げてしまう自分は、まず何を変えればいいか」
第345回「体重が増えると大きな気持ちでいられるようになった」
第346回「気持ちに強弱をつけるということ」
第347回「自分を縛りがち」
第348回「相談するのが苦手」
第349回「敬語でなく横並びの関係を取りたい」
第350回「内向的に育った自分の欠落をどう捉えたらいいか」
第351回~第400回(クリックすると一覧を表示します)
第351回「『なんで』という言葉が多い子供とそうでない子供の違い」
第352回「コンタクトレンズを入れていると頭が痛くなる」
第353回「怒られないための人生を変えるために、まずどうすればよいか」
第354回「啓発本に逃げるような読み方にならないためには」
第355回「どうすればいいリーダーとしての話し方ができるのか」
第356回「自分が薄っぺらいのを直していくにはどうしたらいいか」
第357回「自信を常に安定して持つにはどうすればいいか」
第358回「話すことで気持ちがチャージされる」
第359回「ナルシストと自信がない人」
第360回「朗読をするようになってからビクビクするのが減った」
第361回「大きな目標は、いつ持つものなのですか」
第362回「踏み込まれる怖さ」
第363回「人と人との間に境界線を持つこと」
第364回「怒られやすいタイプ」
第365回「宗教心とモラルについて」
第366回「生育環境が自分より豊かな人に対して壁を作ってしまったり、豊かでなかったことの寂しさや負の気持ちはどうしたらとれるのか」
第367回「桃の味が古い樹と若い木で違うのは」
第368回「自傷について」
第369回「適切な兄妹関係とは」
第370回「野菜を上手に育てられていない心持を具体的にどう直したらよいか」
第371回「甘えをなくし続けることが自分にとって回復し続けることですか」
第372回「AIについて」
第373回「話を要約するのが苦手」
第374回「要領がいい人と、要領が悪い人の差」
第375回「自信の具体的なつけかた」
第376回「物を壊す頻度が多く、どうしたらなくせるか」
第377回「0か100思考をどうしたら克服できるか」
第378回「本を読むとき、作者が伝えたいことが読み取れない」
第379回「シスターの人とどう作業をするか」
第380回「朗読をするとき、面白い場面でも笑わずに読むにはどうすればよいか」
第381回「いつもと違う真剣な空気を怖いと感じてしまう」
第382回「人や野菜の気持ちが汲めないことが多い」
第383回「人をどう評価するか」
第384回「自閉症や発達障害が増えているのはなぜなのか」
第385回「いじられキャラになってしまうのはなぜか」
第386回「小説から現実の世界に戻れないのはおかしいことか」
第387回「ミスをするのが怖い気持ち」
第388回「人と話をするようにどれくらい努めるべきか」
第389回「人との距離感について」
第390回「普通の人になりたいと思うほど、苦しくなったのはなぜ?」
第391回「運転中、後ろから 車に追突されそうなときは」
第392回「窓口で会う、素敵な人のようになりたい」
第393回「人と話すときに遠慮したり、混乱したりして、何も言えなくなってしまう」
第394回「日本の縫製業のこれからについて」
第395回「地で生きていることについて」
第396回「人に言葉を伝えるのが下手だと思う」
第397回「自分に合う服」
第398回「人と目を合わせるのが怖い」
第399回「謙虚な気持ちとは」
第400回「気遣いができるようになるには」
第401回~(クリックすると一覧を表示します)
第401回「写真と自分のイメージがかけ離れている」
第402回「地で生きていると苦しくなること」
第403回「急かされている感じがして焦ってしまう」
第404回「相手の本質がわかるようになるにはどうしたらいいか」
第405回「怒りについて」
第406回「神様を信じる気持ちについて」
第407回「未熟な自分を受け入れることについて」
Copyright © なのはなファミリー 2024 | WordPress Theme by MH Themes