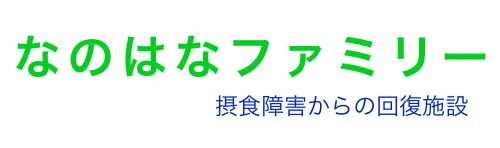外に出ると、太陽の光がまぶしく、わたしたちを包みこんでくれました。
なんていい天気で、心が踊るんでしょう!
「絶好のヨモギデーだ!」
ついに、待ちに待っていた、「ヨモギ摘み」に行ってきました!



集合場所の中庭、あゆちゃんの周りには人だかりが。あゆちゃんの手には、収穫できるヨモギの見本が握られていました。そのヨモギの色、感触を身体に覚え込ませて…。
さあ、ビニール袋を片手に、バディといっしょに、レッツゴー!


バディのあんなちゃんとみみちゃんと、ずっとずっと楽しみにしていたこの日。
昨日のおしゃべりタイムの時間には、ヨモギスポットを探しに歩いてきたりと、わたしたちは、気合十分、準備万端でした!
ということで、今日は、目星を付けておいたヨモギスポットを、回ってきました。


中庭、畑の畦、そして意外だったのは、水やりのタンクの設置してあるふもと。
タンクのふもとのヨモギは、日光があまり当たらないのか、新芽だけでなく外葉も柔らかくて、おいしそうなものがたくさん採れました。

いま桃の選定を進めてくれているあんなちゃんが提案してくれて、いくつかの桃畑にも行ってきました。
桃畑までの坂道を、よっこいしょ、と3人で登っていきました。
息を弾ませながら、「もしかしたら、ここまで来るのは、わたしたちだけかもしれないね」なんて、話したり。
開墾26アールの畑が見えてくると、遠くからでも分かる、ヨモギのやさしい黄緑色が、桃の木の下にびっしり広がっていました。

「あったー!」と3人で叫びました。そしてしゃがみ込んで、ヨモギを摘まむと、ある異変に気がつきました。
「あれ、新芽がない!」
なんと、あのふわふわの新芽が、すでに無くなっているのです。あれも、これも、それも…!
「もうすでに、他の子たちが採りに来てくれてたんだね!」
はっと気がついて、3人でくすくす笑いました。

ヨモギ取りに夢中になってしまって、はじめは3人で並んで採っていたはずが、気が付けば、それぞれあちこちに広がって、もくもくと探しているわたしたち。
黙ってひたすら採っているのも楽しいけれど、それでもやっぱり、3人がいいなあと思いました。
だからか、最後は「採れた~?」と言って、3人が集合して元に戻っていくのも、あたたかくて、うれしかったです。

古吉野に帰ってくると、家庭科室でヨモギの下処理をしました。
帰ってきたみんなが、大集結。みんなの取ってきたヨモギも、大集結。
「洗えたものは、もう茹でちゃうよー!」と、あゆちゃんが、お湯を沸かしてくれました。
こんもり山になっているヨモギを、どさっと、鍋に投入すると…。みるみるうちに、今までの黄緑色が嘘のように、鮮やかな濃い緑色に変身していきました。


変身するヨモギ、そこから立ちこめてくる湯気は、あの爽やかな香りです。
茹で上がったヨモギは、ボリュームダウンしていたけれど、それでも量ってみると、2キログラムありました。
「沢山採ってくることができたね!」「おいしいヨモギもちになるね!」と、みんなの夢いっぱいの笑顔が、うれしかったです。

ところが、思っていたよりも早く、食堂でヨモギとご対面することができました。
りゅうさんが揚げてくださった、ヨモギの天ぷらです。外はさくっと、中はモチッとしていて、最後に、ヨモギの爽やかな味と香りが、ふっと通り過ぎていきました。
みんなでヨモギ摘みも楽しむことができて、こうしておいしく頂くこともできて、わたしはすごく幸せだなあ、と感じました。


そっと道ばたにたたずんでいて、なんてことないものだけれど、誰かにとっては、宝物。こうやってわたしたちに喜びをくれて、わたしたちに春を運んでくれる、そんなヨモギが、「わたしたちの仲間だよ」と、言ってくれているようでした。
ヨモギ、なのはなのみんな、とっても楽しい時間を、ありがとう!
(みつき)
***

***

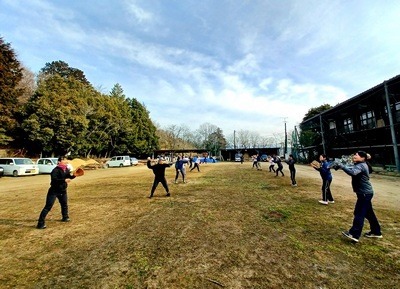

***

桃の樹も、蕾が膨らみ、春支度。
現在、なのはなファミリーでは100本以上の桃の樹を育てているのですが、あんなちゃんを中心に、年間を通して桃の手入れを進める時間はとても濃く、楽しいです。
桃の剪定見習い生として、1月から桃の冬季剪定をあんなちゃんたちと進めてきたのですが、この日で桃の剪定は無事に完了しました。
そして、今季の剪定では今後に繋がる画期的な、剪定方法が確立された年でもありました。

その名も、『クリップ方式』。
これまで、桃の剪定では、それぞれがどの枝を切るか見当をつけた上で、あんなちゃんに実際に切る枝を教えてもらうという、『答え合わせ方式』で進めていたのですが、より、切る人も教える人も分かりやすく、作業の効率化を図るためにもお父さん、お母さんにより生み出されたのが、この『クリップ方式』でした。
『クリップ方式』を一言で説明すると、「切る枝にクリップで見当をつける」というもの。
今までの剪定にただ、クリップが加わっただけで、自分たちもどこを切りたいのかが視覚的にも分かりやすくなったし、自分の頭で考え、桃が剪定された最終的なイメージをしてクリップをつけていくと、剪定を覚えるということも、その作業のやりがいや楽しさも倍増しました。

ここ数日は、晴れていても雨が降っていても、(桃の剪定、したいな)と気がつけば、桃のことを考えてしまうくらい、私の中で剪定が大好きな作業になっています。
私は気分屋といわれたらそれまでなのですが、夏に「一番好きな作業は?」と聞かれたら、「桃の収穫!」と答えてしまうし、秋に同じことを聞かれたら「桃の肥料やり!」と答えてしまうし、今は「桃の剪定!」と答えてしまいます。

きっと、2週間後には「桃の摘蕾!」になり、3週間後には「桃の霜対策」になっているだろうと予測できるのですが、そのくらい、桃の作業は楽しくて、桃のことを知れば知るほど、好きになり、愛おしく感じます。
そして、私が虜になってしまった『クリップ方式』。
1人1本、ノコギリと剪定ばさみ、トップジンに60個くらいのクリップを持ち、各枝にとりついて、まずは切りたい枝にクリップをつけていきます。
この主枝の先端はどこなのか。どの枝を一番強く維持させたいのか、そして維持させるためにどの枝を落とし、どの枝を残すのか。

交差枝や内向枝は基本的に切るけれど、どこまで切るべきか。
枝は邪魔じゃなければ、できるだけ樹に残していた方が、光合成して樹も元気でいられるため、1本の枝を切るのにも頭を使うし、枝がなくなりすぎても樹が弱ってしまったり、樹が日焼けをして痛んでしまうため、上側の芽を残して切るなど、工夫も必要です。
3本仕立てになった桃の樹の下にたち、最初に全体を見てイメージをしてからクリップをつけていくときの、頭と心の使い方や、集中の仕方はすごく心地よくて、楽しいです。
そして、それをあんなちゃんに確認してもらうときも、予測が的中すれば嬉しく、例え外れてしまったとしても、桃栽培のプロであるあんなちゃんから、剪定の考え方や応用編なども教えていただけることが嬉しくて、その都度、自分の中に知識を取り入れ、次に繋げていける喜びを感じます。

最近は、剪定にも大分なれてきて、60個のクリップをつけて3カ所だけしか修正がないときや、第一主枝などのひとブロックに区切って作業をしたときに、修正もほぼないときもあり、達成感を感じます。
あんなちゃんの姿から、あんなちゃんの桃に向かう姿勢や考え方、理想のイメージから桃へ向かう時に大切な心持ちや、頭の使い方をたくさん教えてもらっているし、あんなちゃんたちと8枚の桃畑を周り、桃の手入れをして回る日々が、とても充実していて楽しいです。

桃の蕾も日が延びるにつれて、どんどん膨らみ始めています。
桃の剪定が終わってしまったのは少し寂しいような気持ちもあるのですが、桃は次から次へと、甘い実をつけるために蕾を膨らませ、花を咲かせていくので、私たちも立ち止まる暇はありません。
また、桃の次はスモモの剪定も待っていたり、摘蕾をして、花が咲いては、摘花をして、すぐに摘果や袋がけ、収穫と桃の1年は動き続けます。
私も少しでも、あんなちゃんを中心とした桃栽培の役に立てるよう、しっかり動いて、覚えていきたいし、これからの季節が楽しみです。
(ななほ)
***

崖崩れハウス前上畑に立つ3本の煙突。
そこにあるのは小さな籾殻燻炭工場。
朝7時半から、工場はせっせと始動しています。
風に揺れ、煙突3本、同じ方向に煙をたなびかせながら、3つの工場は動いています。
少しずつ少しずつ、じっくりじっくりと、低温で、燻されていきます。

黄土色の籾殻の山の内側から、徐々に徐々に、黒いものが浮き出てきます。それはまるで、木の板に、墨で書いた文字が浮き出てくるみたいで、スローな、魔法のかけられている山みたいでした。
燻し始めてから、およそ3時間半。表面の5割ほどまでが黒色に染まってきていました。
まりのちゃんが、早すぎず、白く灰になってはならず、ベストな切り返しのタイミングを、燻炭の気持ち、そして、燻炭を待ちわびている種や苗の気持ちになって量っていました。その優しく鋭い目つきは、職人であり、お母さんでした。

そして、ここだというタイミングでの切り返し。
内側のよく燻されたものと、外側のものとをゆっくりと返しました。
近づいてよーく見て見ると、ぴくぴくと、「頑張っているよー!」「僕のことみてー!」とでも言っているかのように、小さな体を一生懸命に動かしているのでした。内側からの熱の圧力と、風との力なのでしょう。しかし、それが、命ある籾殻が呼び掛けているように見えて、本当にかわいかったです。

最後には、サツマイモからのサプライズがありました。
私たちに気づかれないようにと、ひっそりと、籾殻の中にサツマイモがかくれんぼしていたのです。見つけたときには、もう焼き芋に。低温でじっくりと焼かれた焼き芋は、皮がパリッとはがれて、ほっくりとした焼き芋になっていました。

ナスに、ピーマンに、トマト―。
これから次々に夏野菜の種まきが始まります。それに向けて、3山分のたくさんの籾殻燻炭を作ることができて嬉しかったです。
(ちさ)
***


***


***


***