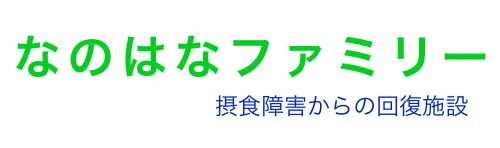5月23日のなのはな

今年、黒大豆を植える畑に、苗床を作って黒大豆の種まきをしました。
黒大豆を植えるのは、滝川横、奥の畑と、梅見畑で、合わせて26.3aあります。
それぞれの畑の一角に、高畝を立てて、そこで苗を育てます。
黒大豆は、湿害に弱くて、今までも芽が出る前に種が腐ってしまい、発芽率がよくなかったことがあります。
今回は、畝を平たくせずに、馬の背型の高畝にすることで、雨が降っても水はけがよくなるように作りました。実際、白大豆の種まきをしたときに、苗床を台形型にするよりも、そのように作るのが、芽が出揃って良かったと感じてもいます。

種のへそを下にして1粒ずつ、まき溝に置いていき、種まき培土を覆土して、乾燥防止にもみ殻を薄くまきました。水やりをして、最後に、寒冷紗をかけておいています。
4日、5日で発芽するはずで、水やりも多くやりすぎると種が腐りやすいので、丁度良くできるように見ていきたいです。
現在、他の豆類は、白大豆とササゲを苗床で育てています。5日前に種まきしたササゲは、ほとんどの芽が出かかってきています。
白大豆は、今週から本葉が伸び始めていて、定植の準備をするところです。2枚の畑で苗床を作っているのですが、先に種まきした畑では、畝を高く、丸く整えましたが、あとからまいたほうは、高畝でも台形型にしました。しかし、先にまいたほうが、芽の出揃い具合や、その後の成長が良いと感じ、畝の形も関係しているのかなと思います。

寒冷紗をはぐるタイミングも大事で、それも発芽の出揃い具合に関係していると感じます。最初は乾燥しないように、豆が暑さで傷んだりしないように紗をかけているのですが、芽が地表に持ち上がり、伸び始める手前で、そのままではすぐに苗が徒長してしまうので取らなければいけません。少し早いと、せっかく発根した豆が暑さで傷んだりしてしまいやすいです。
豆類は、種まきするとすぐに発根するのだと思いますが、それが出揃って良い苗にするには、毎日気を遣わなければいけないことを感じます。
黒大豆も、どの苗も綺麗に出揃って上手く育つようにしたいです。
(まりの)




夜の図書室からは、7本のアコースティックギターが奏でる音色が流れてきます。
いつもギターや木版画を教えてくださっている藤井先生が催される、写真・版画・陶芸の4人展「それぞれの景」が、5月25日から始まります。展覧会のオープニングに、藤井先生が選んでくださった曲目のギター・アンサンブルを演奏します。演奏をするメンバーは、夜、消灯の間際まで、じっくりと、充実した練習時間を取ることができました。
また、展覧会前さいごの木版画教室がありました。展覧会の一角に、藤井先生の版画教室で制作した私たちの作品も飾らせていただけることになっています。制作が長引いてしまったものもありましたが、藤井先生が、たくさん刷った版画のなかから最も良いもの、額縁に似合うものを見てくださり、すべての作品を額縁に収め、無事に、展覧会の準備を整えることができました。藤井先生が、私たちが版画を作る過程と、一つひとつの作品を、大切に、大切にしてくださり、とてもありがたく、嬉しいです。
明日は、展覧会の搬入とセッティング、そしてギター演奏のリハーサルがあります。準備が良い形で運べるよう、精一杯、頑張ります。