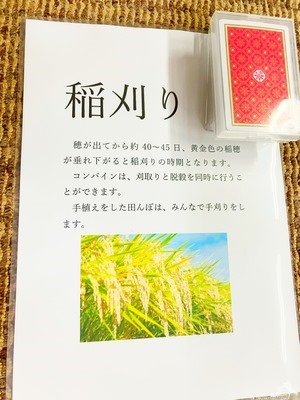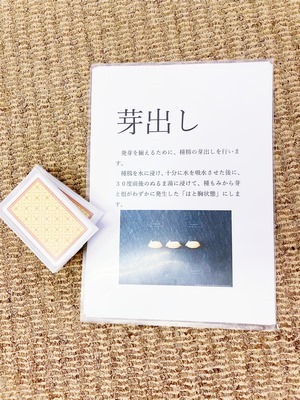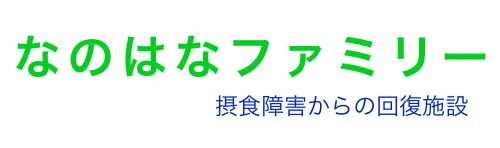5月6日のなのはな

開花から20日。摘果1巡目のタイムリミットが3日後に迫り、無事に間に合わせられるよう急ぎ足で、あんなちゃんを中心とした6人のメンバーで摘果を進めました。パラパラと小雨が降る中、かっぱを着ての作業でしたが、ほどよく風も吹いてきて涼しくて、摘果に集中しやすかったです。
摘果1巡目は、30センチに2個くらい残るように、実を摘んでいきます。
もう桃の実は、2,3センチほどの大きさに膨らんできていました。いびつな形をしていたり、小さすぎたり、虫食いの後があったりする実を落として、なるべく大きくてきれいな実を、枝の根元から3分の2くらいのスイートスポットに残せるように意識しました。


ゴールデンウィークの期間、山小屋キャンプやつつじ祭りなどのイベントで、摘果も少し遅れてしまっていたけれど、この日は1日を通して、がっつりと進めることができました。
開墾26アールの清水白桃は、まだ若い木だったこともあるけれど、6人で1本の木に取りつくと、テンポよく次の木へ進んでいきました。
あんなちゃんが全体を見回ってくれて、的確に、いい収穫に繋げられる摘果をするには、何に気を付ければいいかを、その都度伝えてくれました。清水白桃は、短果枝にいい実がつきやすいと言われているため、2~15センチくらいの短い枝の実を大切にすることも、教えてもらいました。
桃の木に対して、摘果の作業に対して、メンバーに対して、より良い手入れができるように心を遣い続けているあんなちゃんが、すごいなと思いました。

休憩時間には、みんなで輪になって山手線ゲームを行いました。お題は、『昆虫』や、『水に関するもの』『今までにウィンターコンサートで演奏した曲』など。
6人と人数が少なかったので、すぐに順番が回って来て、難しかったです。私は、昆虫に関しては、ルリボシカミキリ、クワカミキリ、ゴマダラカミキリ、キボシカミキリ、クビアカツヤカミキリ、と全部イチジクの天敵であるカミキリムシで乗り切りました。(ルリボシカミキリだけは天敵ではありません)
それ以外のテーマでは頭が真っ白になって、2回も負けてしまいました。でも、すごく面白くて、みんなで笑い合うと心がほぐれました。休憩後は、集中力が回復して、摘果に向かうことができました。


今日1日で、開墾17アールの日川白鳳2本、開墾26アールの清水白桃11本が終えられました。かなり進めることができて、達成感を感じました。
次に進めたいのは、開墾26アールの白皇です。白皇は木が大きいため、手強くなってくると思います。最後に少し取り掛かったとき、実の数も多くて、やりがいがありそうだと感じました。その分、大きくてきれいな実も、数多く残せるのではないかと思います。

目標はあと2日。摘果1巡目をいい時期に終えられるよう、できることを頑張りたいです。
(りんね)
***

崖崩れ下道路側ハウスで、リーフレタスとロメインレタスを育てています。どちらも、結球しないレタスで、育てるのははじめてです。
リーフレタスは、波打った葉が幾重にも重なっていて、まるでお姫様のドレスのスカートみたいです。ロメインレタスは、濃い緑色で、普通のレタスよりも少し肉厚で、こちらは落ち着いたロングドレスのような雰囲気です。
レタスのハウスに行くと、レタスたちのおしゃべりが聞こえてきそうです。「見て、私のこのフリフリの葉」「私も奇麗でしょ」


今日はついに、このレタスたちの初収穫をしました。最初に、ロメインレタスを株ごと収穫しました。どの株も、「私を食べて」という声が聞こえて来そうなくらいに良い大きさです。株元に包丁を入れるとき、どきどきしました。収穫したロメインレタスを手に持つと、ここまで育ったレタスを愛おしく感じました。普通のレタスよりも緑が濃くて、少し肉厚で、シーザーサラダにすると美味しいそうです。ロメインレタスがなのはなの食卓にデビューする日が楽しみです。

リーフレタスは、下葉を摘むようにして収穫しました。葉が優しい手触りで、手で下葉を摘むと、パリッと優しい感触がして、レタスの柔らかい香りがして、手の感触だけでも美味しい、と思いました。洗ってちぎって、お椀に入れて食べたら、どれだけ美味しくなっちゃうんだろうと、収穫しながらもにやけてしまいました。
初収穫のロメインレタスとリーフレタスを、ブーケのようにして、畑の「シンリータチーム」のみんなで、お父さんとお母さんにプレゼントしました。お父さんとお母さんがとても喜んでくれて、嬉しい気持ちになりました。なのはなの食卓で、みんなとレタスをいただけるのも、とても楽しみです。
(えつこ)
***
今週末は、家族みんなでの播種。
なのはなの米作りのための、重要なイベントです。
今日は、その播種の前段階としての、比重選を行いました。

「比重選」は、良い種籾を選ぶために行う行程です。
種籾の中身は主に胚乳で、発芽から初期生育にかけての必要な栄養素を含んでいます。
この胚乳が多い種籾が良い種籾なのですが、胚乳が多いのか少ないのかを、見た目だけで判断することは難しいため、硫安水に籾を入れ、浮き上がった軽い籾を取り除き、沈んだ重い籾を種籾にする。といった作業です。
塩水を使った「塩水選」が一般的ですが、なのはなでは、盛男おじいちゃんに教えてもらった硫安水を使って行います。

今年は、5枚の田んぼが増えたため、籾の量も例年より多く、お風呂場で比重選をして、体育館に干すことになりました。
午前中に、お風呂や体育館の掃除や、道具の準備を進めて、午後に比重選の作業を行いました。
まえちゃんが最初に、比重選を行う順番(紫黒米→餅米→うるち米)と、干すときに、お米の種類が混ざらないように注意することを説明してくれて、比重選がスタートしました。

種籾は4キロずつ水につけていきます。
先ず始めは紫黒米。紫黒米は真水で行います。
種籾を水に入れて、浮いてきたものを取り除きます。
次に餅米。ざるに入れた種籾を、40リットルの水に8キロの硫安を溶かして作った硫安水に入れ、浮いてきた種籾を取り除きます。その後、2段階に分けて、硫安を洗い流します。
硫安がついていたり、籾が少しでも剥がれると発芽できない、と、まえちゃんが教えてくれたので、しっかりと洗い、そしてそっと、ザルから上げる。ということに注意をして作業をしました。

餅米の後はうるち米です。餅米の時よりも4キロの硫安を足して、硫安水を作り、それに種籾をつけて、種籾を選別していきました。
脱衣所で、どれみちゃんがお米を量って水につける準備をしてくれて、お風呂の中で、まえちゃんが比重選をして、お米の選別、洗い流しをしてくれて、私がまえちゃんとどれみちゃんの橋渡しをするといった流れ作業で進めていきました。
そして、選別された種籾を、まことちゃんとなつみちゃんが、体育館に運んでくれて、新聞紙の上に干してくれました。
ひと目で品種が判るように、2人がしっかりと名前を付けてくれていました。

まえちゃんと一緒に作業をさせてもらって、まえちゃんの迷いのない判断や、潔い動きを見て、改めて、効率良く動くこと、無駄なく動くことで、作業が楽しくなることを感じました。私も、もっと、迷いなく潔く行動することをしていきたいと思いました。
なのはなで、盛男おじいちゃんが教えて下さったこの方法で、これからも比重選をしていけることが嬉しいし、その作業に携われることが嬉しかったです。
盛男おじいちゃんからもらった、大きな財産だと思うし、おじいちゃんの笑顔が思い浮かんできて、優しい気持ちになれました。

これから、なのはなのお米作りがスタートします。
今年から5枚の田んぼが増えたので、家族みんなで協力して、みんなの笑顔や優しさが、たくさん溢れるお米作りが出来たら良いなと思います。
(よしえ)