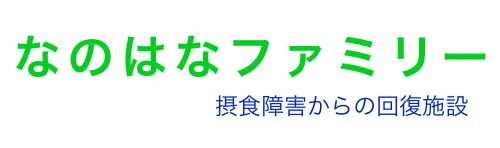6月28日のなのはな
味噌の天地返しをしました。
私は2月に味噌の仕込みをしたのですが、4か月ぶりに味噌たちに会えて嬉しかったです。
天地返しをすると、発酵が促進されるということを、ゆりかちゃんに教えてもらいました。天地返しは絶対にやらなければいけない工程ではないそうですが、やった方が絶対美味しい味噌になるだろうなと思いました。

冬に米糀と味噌の仕込みをするときは、毎回、それぞれの特徴を踏まえて、チームや味噌に名前をつけているのですが、今年は、1弾の「味噌の戦士ぱわふわレンジャー」のチームと、2弾の「御米~豆(およね~ず)」チームが味噌を仕込み、私は御米~豆チームの1人でした。
糀の最初の手入れで、お米が動き出したときの感動や、夜の糀の見回りがドキドキしたこと。米糀に名前をつけよう、と夜の手入れをしているときにチームのみんなで名前を考えたことや、糀菌たちが暴れて温度が高くなった時に、扇風機で対策したことなど、楽しかったことが思い出されて、嬉しい気持ちになりました。
白大豆味噌の「白百合 米花(しらゆり べいか)」と黒大豆味噌の「味噌川 黒美(みそかわ くろみ)」。御米~豆のチームはお姉さんメンバーだったので、糀の名前も大人っぽく考えました。私も気に入っています。

天地返しでは、最初にぱわふわレンジャーの「パワフワちゃん」に取り掛かりました。
樽の蓋を開けてみると、
「わぁ~綺麗」
澄んだたまり醤油ができていて、状態も良く、とっても綺麗でした。

味噌からは甘い香りがしていました。パワフワちゃんという名前のように、ふわふわしていて、柔らかかったです。触り心地も良かったです。
空気を抜くようにしながら味噌を別の樽に入れていき、平らに均して、密閉しました。
初めて天地返しをするメンバーもいましたが、作業はとってもスムーズに進み、天地返しが完了しました。

御米~豆の味噌は、パワフワちゃんと比べると、お姉さんっぽくしっとりしていました。黒大豆味噌の“味噌川 黒美”は、白大豆味噌とは香りも違って、私は豆の香りが強いなと思いました。
白大豆味噌の香りと、黒大豆味噌の香り、どちらもいい香りだったのですが、香りの好みが天地返しをしたメンバーで分かれました。私は白大豆味噌の香りが好きだなと思いました。


どの味噌も発酵が順調に進んでいるようで、味噌の状態も知ることができて嬉しかったし、天地返しをして、より美味しい味噌になってくれたらいいなと思います。
次に会えるのは3年後です。
長いようだけれど、3年後に樽が開かれ、みんなの食卓に届くときが楽しみです。
(しなこ)
***
桃畑では、瞬く間に「はなよめ」の収穫が一段落し、桃チームは1日を通して、次に穫れ始める品種のネットがけや手入れ、桃に雨を吸わせないためのブルーシート敷きなどを進めました。
古吉野なのはなの屋内では、ミシンが威勢よく動き続け、桃にかぶせる巨大なネットを縫い合わせています。ネット作りチームは、昨日は半日で150メートルを縫い、今日は午前に190メートルを縫い、と絶え間なく作業の効率を上げていっています。
次の作業に必要なネットをロールから切り出すときは、長い廊下を利用してネットをのばし、長さを測りました。「こんな長い廊下があって嬉しい」桃の樹を守るベールのような真白いネットを抱えながら、作業場に戻る3人は、そんなふうに話していました。




12時を回ると、真夏の夕立と同じような雷雨がやってきましたが、やがて空も落ち着いた午後からは、桃の手入れと並行して、『ヤットサ節』『四つ拍子』の盆踊り練習などを行ないました。
***
夜の勝央文化ホール。音響反射板の天井がおりて、どこか秘密の洞窟めいた舞台。オレンジの明かりがほんのりと回った洞窟にこだまするのは、金太郎の祭ばやしです。

勝央金時太鼓のメンバーはこの日、主に『金太郎ばやし』の練習を行ないました。これまで練習してきた締太鼓、チャンチキ、宮太鼓のリズムに、新たに囃子太鼓と大太鼓のリズムを加えての練習です。
今日は順に役割を回しながら、それぞれのパートに慣れていきました。今日からこの曲に取り掛かるメンバーも、「天テケ ステツ 天ステステツ……」と口唱歌で何度もお囃子の曲を唱え、練習しました。


これまでは主に締太鼓、宮太鼓、大太鼓を使った楽曲を演奏してきた私たちですが、それの太鼓で打つ『金太郎ばやし』ならではの跳ねたリズムに、よく通るチャンチキの音が乗ると、独特の熱が増していく感じがあります。練習していると、自然と嬉しくなります。けれど、自分の内だけではなく、見ている人が引き込まれるほど、いかによく演じて楽しげに打つか、躍動感のある動きで演奏するか、というのも、この曲の大切なところです。
これから篠笛や組太鼓などの楽器も習得して、みんなで自在にこの曲を演奏できるよう、練習に取り組んで行きたいです。
(かに)