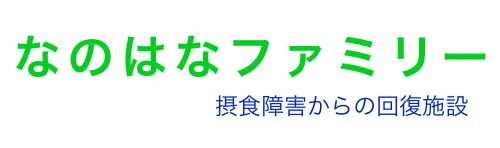9月26日のなのはな

「こんなにダイナミックな畑作業しているの、世界中で私たちだけかもしれない!?」
思わず、そう言いたくなってしまうような作業の内容は、バナナの株分け。
いつも私たちにアコースティックギターを教えてくださっている藤井先生から、以前、「3尺バナナ」の株をプレゼントしていただき、その子たちを株分けして吉畑ハウスのバナナハウスへ植えました。
その時はまだ、私の膝丈くらいしか草丈がなかったバナナの株たちでしたが、夏場の水やりでたっぷりの水を吸い、太陽の光を浴びて、今では大きいもので3メートルを超える大株にまで成長しました。

(あれ? 3尺バナナって、3尺だから90センチくらいまでにしかならないんじゃないの?)
と思う方もいると思うのですが、実は3尺バナナを露地栽培で育てる場合、3メートルほどにまで成長するのです。
もちろん、鉢植えにして室内で育てる場合などは、強制的に根域制限がされるため、3尺の背丈でも実をつけることができるのですが、なのはなファミリーでは広々とした2重構造になったバナナハウスいっぱいに、バナナが葉を茂らせ、元気いっぱいに育っています。
そんなバナナたちは今のところ、来年の夏に実をつける予定。そのため、実をつける予定の親株に栄養がいきわたるよう、株分けを行いました。

株分けと言っても、観葉植物や多肉植物のような株分けを想像してはいけません。先ほども書きましたが、バナナは現在、大きなもので3メートルを超えているのです。そのため、とてもダイナミックで、迫力のある株分けとなりました。
吉畑手前ハウスでは全部で5株のバナナを栽培しているのですが、その子たちから新たにたくさんの芽が出て、株が増え、今では草丈15センチほどの小さな子も含むと、30株以上にまで増えているのです。
そのため、株分けではできるだけ根を傷めないように配慮したうえで、スコップを使いバナナの株を切り分けて掘り起こし、小さな株は植木鉢やポットへ、大きな株は肥料袋という名の巨大鉢植えへと植え替えました。

最初に「よし、じゃあやってみようか!」とバナナハウスへ入った時は、一度入ったら出られないほど、前を見ても後ろを見ても、右も左もバナナで、(これは、まいったな……)と内心、ヒヤヒヤしました。
でも、できるだけ深く、根を傷つけないように1株、バナナを掘り起こしてハウスの外へ運び出してみると、それだけでも空間が広がり、「次は、私を掘り起こして」というように、次のバナナの株が顔を出しました。
バナナはもともと、東南アジアが原産の植物のため、暑さには強いけれど寒さには弱い。そのため、冬が来る前に株分けをしないと、親株は枯れてしまう恐れがあります。
そのため、今回の株分けはバナナにとって、手術のようでもあったけれど、後のことを考えると救いのような作業で、私たちも責任感を持って行いました。


実際に株分けをしてみると、「こんなにも、バナナが育っていたのか」「こんなにたくさんのバナナが、あのハウスに入っていたのか」と驚くほど、バナナの株は大きく、とても綺麗で、一気に日本から南国へ旅行に来たような気分になりました。
まなかちゃんとまよちゃんがマクワウリスムージーを片手に、バナナの前に座っていれば、そこはフィリピンやハワイのバナナ農園のようで、このまま、フラダンスを踊ってほしくなってしまいます。

株分けをしたバナナたちは、これから室内へ運び、冬越しをして来年の春に、新たにハウスへと植え付ける予定です。
寒さに弱いバナナにとって、少しでも育ちやすく、居心地のよい環境が作れるようにしっかり見守っていきたいです。
また、今回、株分けをしたバナナたちが実をつけるのは2、3年先のことになるのですが、それまでになのはなのみんなとバナナ栽培に対する知識も共有しあい、いつか、
「桃やブドウ、イチジクだけではなく、バナナもなのはなで栽培できる」
「なのはなで食べるヨーグルトにはいつも、なのはな産のバナナが入ってる!」
と言えるくらい、バナナを育てていきたいなと思います。


そして、今、バナナハウスに残った親株たちは、上手くいけば来年に実をつけます。なのはなファミリーの冬は、雪が何度も積もるくらいに気温が低くなるのですが、防寒対策でビニールハウスの補修や農電ケーブルの管理も行い、上手くバナナが冬越しできるように頑張りたいです。
なのはな産のバナナをなのはなのみんなで食べられる日が来るよう、これからもバナナに愛着を持って、手入れや管理を行っていきます。
(ななほ)
***

午後の作業で、太ネギの3回目の土寄せをしました。
昨日の追肥ツアーでたっぷりと牛肥をやった太ネギに、今日はしっかりと土寄せ。追肥後すぐのベストタイミングで太ネギに土寄せができて嬉しかったです。
畑に着き、リーダーのりんねちゃんが、太ネギの畝は1畝が長いから全員で1畝に入って1畝ずつ終わらせていこうと言ってくれて、1畝に等間隔に入って進めていくことになりました。午前の時間に、まちちゃんとどれみちゃんが管理機で畝間を耕してくれていて、クワを入れただけで土の細かさ、軽さが分かります。
太ネギは勢いよく葉を伸ばしていて、畝の反対から土を引き寄せるようにクワを動かすと葉を傷める心配をしなければいけませんでした。そこで、自分たちが太ネギのそばに立ち、自分の足元に土を引き寄せるようにしながらネギに土を寄せる動きに変えました。その方法に変えると一気に土を寄せやすくなりスピードも上がったなあと思います。そんなふうに提案をしてくれたのもりんねちゃんでした。土寄せのあとにもやりたい作業があり、急ぐ気持ちもあったけれど、りんねちゃんの、太ネギに優しい土寄せの仕方でやろうという心遣いがとても綺麗だなと感じました。太ネギの分岐点までしっかりと土を寄せることができて嬉しかったです。

畑の半分の土寄せが終わりみんなでお茶休憩をしたあと、後半になると更にスピードも上がって土寄せが進んで行きました。最後は助っ人も駆けつけて来てくれて、1時間10分ほどで太ネギの土寄せが終わり、残り時間で他の野菜の中耕もできて嬉しかったです。太ネギは今回で3回目の土寄せが終わって、あと1回ほど土寄せをしたら収穫までの土寄せが完了します。
今回の土寄せでまた更に太ネギがすくすくと生長していくのが楽しみだなと思います。
(よしみ)