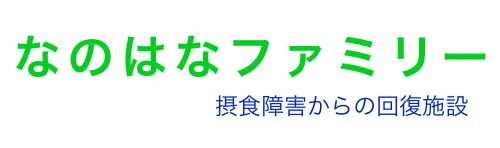5月20日のなのはな
なのはなに新しい家族がやってきました!
その名は……。
『レッドくん』
『ブルーくん』
『ウイングちゃん』
『モアちゃん』
『かるちゃん』
そして、『マックスくん』です!
玄関下で、出番をまだかまだかと待ち構えていた彼、彼女らが、ついに今日みんなの前にお披露目され、お父さんによる使い方の講習会が開かれました。

まずは、オートモアーのレッドくん。レッドくんとブルーくんは、使い方が同じなので、代表で、レッドくん。
AM61Bと表示されているレッドくんは、60センチ幅で草を刈る、主に平地担当の自走式草刈り機。
お父さんが、胴体を持ち上げ、本体下についている刃を見せて下さったのですが、60センチほどの平たいバーがついており、先端は刃の形状になっていました。

そのバーが回転することによって草が刈れる。そして、その草や小石は胴体の右方向に飛んでいくため、カバーが右側についており、草を刈るときには、窓ガラスや道路など、飛ぶと危険があるものがあったら注意し、飛んでも害のないほうを右に見ながら、場合によっては、バックギアを使いながら刈っていく、と教えてもらいました。
バックだと逆回転になりそうなイメージもあったのですが、回転する方向は変わらず、タイヤだけが逆回転になり、バックでも刈れるのが、便利だなと思いました。

刃の回転のオン・オフや、前進・後退レバー、そしてデファレンシャルギアをロックすると凸凹道でも脱線せずに走ることができるということで、凄いなと思ったのと、使いこなせるか分からないけれど、使いこなせたら楽しそうだなと思いました。
実際にお父さんが、古畑でエンジンをかけて、草刈りをして見せてくれたのですが、スピードが想像以上に速く、草を刈った後の草丈が一定で、綺麗でした。あっという間に1往復ができて、驚きました。

続いては、ウイングちゃんの登場です。
ウイングちゃんは、その名の通り、刃の周辺が羽根のように開閉する形で、カバーごと刃の角度を変えることができ、畦の上面と垂直面を同時に刈るときに便利な自走式草刈り機です。
畦の角度に合わせることができるのが、一番の魅力です。刈払機だと、畦を綺麗に刈るのは時間がかかったり、難しかったりするけれど、ウイングちゃんの手にかかったら、歩くスピードで一気に刈れてしまうのだから、心強いです。

刃は、プロペラの様なものが2つ、ついています。
ウイングちゃんのボディーには、『軽刈~る』と書いてあるのですが、軽々刈れるのかなと思いました。
お父さんが古畑の畦を刈ってくれました。羽根が折れ曲がる様子にもみんなで、「凄ーい!」と感動。そして、角度のついた畦も綺麗に刈れていて、田んぼの畦を刈るのが楽しみになりました。
そして最後に、カルマックスのカルちゃんの登場です。
カルちゃんはよく見る自走式草刈り機だ! と思いました。畑作業をしていると、地域の方が法面を、犬の散歩をするように、このタイプの自走式草刈り機を引いていらっしゃるのをよく見かけます。
柄の部分が長く、斜面を刈るのに便利な自走式草刈り機。柄は動かすことができ、自分が本体の後ろにいったり、前に行ったり横にいったり、あるいは法面の角度に合わせて上下に調整したりと、自在に変えられます。

このカルちゃんは、その名から思わせる通り軽くて、重さ50キロほどで、オイルは、2サイクルエンジンオイルで、50:1を使うと教えて頂きました。
このカルちゃんは、走りながらでも操作できるというところが便利で、本当に散歩をしているように使えるという優れもの。
こちらも実際に、お父さんが草を刈って見せてくれました。


上記の3つのタイプが2台ずつ、なのはなファミリ-に仲間入りです。
平地、畦、斜面と用途に応じて使い分けをし、自走式草刈り機と刈払機を併用して草刈りを進めることで、効率をアップし、速く綺麗に草刈りを進めることができる!
なのはなファミリーでは、田畑がたくさんあるため、とても心強いなと思いました。そして、この夏の草との闘いに勝てそうだと、希望を感じました。
そして、講習会のあとの作業では、早速オートモアの、レッドくんとブルーくんと共に、山桃畑に行きました。
あゆちゃんが、軽トラへの載せ方やロープの縛り方を伝授してくれて、ロープを縛るのは、見るよりも、実際にやってみると身体に入れて覚えることができて、とても有り難かったです。
レッドくん、ブルーくんを併用し、木の周りやポール周りなど、刈れない所、刈りにくい場所の所は刈払機で刈り進めていきました。

私は、ブルーくんを使わせてもらったのですが、エンジンのかけ方や作りは、刈払機や管理機と似ている為、すぐに覚えることができました。
胴体は大きいので、重いイメージがあったのですが、エンジンをかけて、前進にすれば勝手に前に進んでくれるので、自分は支えるだけ。
方向転換もらくらくできて、凄くスムーズに操作も刈ることもできました。
直進だけでなく、前進と後進を上手く使って木と木の間も刈ることができ、徐々に使いこなせるようになっていきました。

感想は、凄く楽しかったです。速くて綺麗。草丈を一定に刈ることができて、草が溜まらず、細かく散らばるので、刈ったあとの畑がいちだんと綺麗に見えました。
刈払機で刈れないところは、鎌で綺麗に刈って、畑一面綺麗にすることができました。
刈払機で草を刈るのも、よりスピーディーにできたように感じました。自走式草刈り機に負けまいとする気持ちや、楽しさや、使う筋肉が違うことで、身体も心も軽く感じました。
これからの草刈りが、ますます楽しみになりました。
次は誰かに伝える側として。草刈りを極めていきます。
(ひろこ)

******
雨が上がって、また、畑作業を再開することができました。
「なのはなの夏の作業と言えば、これ!」
と言いたくなるのが、アスパラの追肥だなあと感じます。

アスパラ畑の面積自体は小さめで、6畝しかないけれど、エルフ(1.5トントラック)の3分の2杯もの量の牛肥を、追肥します。
支柱で区切られた1スパンにつき、テミ5杯の牛肥を撒いていきました。バケツリレーで繋いでいって、先頭のせいこちゃんとわたしが、撒いていきました。
畝間は、まるで陸上の直線トラックを走っているよう。みんなが「はい!」と言って、牛肥と一緒に笑顔も送ってくれて、ますます楽しくなりました。

まなかちゃんが、
「アスパラが伸びていくところを想像しながら、頑張りましょう~!」
と明るく声を掛けてくれました。
こんもり山になった牛肥で、すっかり隠れていくアスパラ。けれど、なんだかとても気持ちよさそうです。
今まで、アスパラガスと聞いても、こんなに肥料が大好きな食いしん坊さん、という印象はありませんでした。
こうやって追肥をすることで、わたしたちは、あのアスパラの意外な一面も、その美味しさの秘密も、ぜんぶ知っているような気がして、すごくうれしくなります。追肥の量も多ければ、達成感も大きいです。
食いしん坊のアスパラさん。畝の上に顔を出してくれるのが楽しみです。

続いて、夕の子畑のタマネギを抜き、畑に干していきました。
半年という長い時間を経て、タマネギと会うことができました。今日は、大きなものから優先して抜き、畝間に置いて乾かしてきました。
畑に着くと、じゃんけん大会が始まりました。じゃんけんに勝利したのは、せいこちゃんと、ふみちゃん!
このふたりが、タマネギの上から消石灰を振りかけていってくれました。まなかちゃんイチオシの、
「ティンカーベルになれる、とっても楽しい作業」
だそうです。いいな~!

真っ白になったタマネギ。マルチの膨らみを見ると、球が大きくなっているのがよくわかります。中でも、本当に大きなものは、マルチの穴が伸びんばかりに盛り上がっていました。
茎を持って引っ張ると、ズボっという音とともに……
「ああ! 大きい~!!」
思わず歓声を上げてしまったし、何度も何度も、大きなタマネギが出てくるたびに、「ねえ、大きいよ!」とみんなに伝えてしまいました。


今日は、畑の3~4割ほどのタマネギを引き抜いてきました。干されたタマネギがずらっと並んでいる光景に、みんなで、うれしさいっぱいで帰ってきました。
雲が流れて、照らされた光で、タマネギの薄皮のオレンジ色が、きらきらとしていました。太陽と同じ色だなあ、と感じました。
またしばらくしたら、収穫して、古吉野なのはなで迎えられるのが待ち遠しいです。
(みつき)

***
午後は、田んぼの見回りをしながら、代掻きへ向けた水入れの準備、溝さらいなどの整備も行っていきました。
地域の方の田んぼにもだんだんと水が張られ、空や山々を静かに映す、夏の田んぼの風景が広がっていっています。
私たちも、水入れ前の田んぼの排水口を、板や土嚢、肥料袋などを使ってしっかりと止めていきました。

また、諏訪新田んぼの入口前を通っている土管は、かねてから泥が詰まっているようで、しかし約5メートルほどの長さが地中にあるため、なかなか泥を取り除くことができない、という状況でした。そこで今日は、古タイヤを使った画期的な詰まり解消法を、お父さんが教えてくれました。
まず細長い竹を、土管の入り口から出口まで通し、片端に長いワイヤーロープを結びつけました。そして竹を反対側から引き抜くことで、ワイヤーを土管の中に通すことに成功。
つづいて、ワイヤーロープの片端は古タイヤに、もう片端はトラクターに結びつけました。
このタイヤを引っ張り、土管のなかをくぐらせて泥づまりを取るのです。


お父さんが、ワイヤーロープにまっすぐ力が伝わるよう調整しながら、ゆっくりとトラクターをバックさせていきます。土管にタイヤが入る瞬間だけ、力を加えてタイヤを押し曲げてやると、土管のなかにずるりと入っていったタイヤが、やがて、たくさんの泥を押し出しながら、土管をくぐり抜けてきました!
タイヤの大きさを変えて2回、この作業をし、出てきた泥を鍬でさらうと、土管の中や周囲の泥がなくなり、水がきれいに流れるようになりました。なんだか痛快で、土管が綺麗になってとても嬉しかったです。