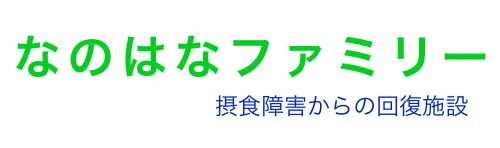2月22日のなのはな

90本の栗の木ファミリーは、今日はみんなで仲良く日向ぼっこ。
久しぶりの温かな日差しと、時折吹いてくる風の心地よさを満喫中。
だけど、そうしながら少し気が付いてしまったよう、少し伸びをしてみると、隣の彼と、ずいぶんと枝がぶつかっちゃうってことに。
生まれてからこの方、ずっと家族みんな仲良くこの畑で大きくなったけれど、もう全員で暮らすには少し狭くなってきてしまったなってことに。
もうすぐかなと思っていたら、チェーンソーの音が聞こえた。2つのチェーンソーがやってくる音が、近づいてくるのが。
さみしいけれど、いよいよ間伐の日のよう。30本の仲間たちは旅立ち。
伐採されてしまう彼らの分まで、太く強く生き抜こう。
今なお畑に残っている栗たちは、こんなことを思っていたのかな、と思いました。

私たち伐採隊は、安全を第一に、豪快に、慎重に作業を進めていきました。ロープで太い栗の木を引っ張ろうと踏ん張ると、追肥して間もない鶏糞にヌルっとすべりかけたり、ツンとスパイシーな木の粉を、真正面から浴びてしまったり、そんないろんなプチハプニングもありながらも、1本ずつ着実に進めていきました。
私も少しチェーンソーを使わせてもらいましたが、チェーンソーに負けないだけのパワーと豪快さと繊細さを持つのはハイレベルなことで、先頭を切ってチェーンソーを振るっている須原さんや、あゆちゃんが本当にかっこよかったです。

私の思う今日一番の伐採の楽しさは意外なところにありました。それは整理整頓の楽しさです。
チェーンソーで次から次に切り倒された幹や枝を、だいたい同じ長さに整えて小束にしていく。
足元であっちこっちと広がっていたものが分解されて、整えられていく様はとても気持ちがよかったです。

5時頃、最後の1本の切り倒しが終わったときは、とても達成感がありました。
最後の1本は、今日一番の老木の太いものでした。最後の最後、チェーンソーも疲れ切って切れ味が落ちてはいましたが力を振り絞ってくれて、みんなで「よいしょ、よいしょ」と綱引きのように倒した時間が、とても嬉しかったです。

ブナ科の栗の木は、マイタケを筆頭にキノコの榾木にも向いていると教えてもらいました。作業をしながら榾木に使えそうなものをこっそりと集めていました。
広々とした畑で、のびのび育つクリも、そして、キノコも、色々楽しみです。
(ちさ)

***
今年初めての種まきをしました。
吉畑手前ハウスの中には、電熱線を埋めた苗床があります。なのはなファミリーでは毎年、春夏野菜の育苗は、この苗床で温度管理をしています。一昨日から、設定温度を20度にして、ビニールを2重にかけて、今日から始まる育苗に向けて温めておきました。

第1弾の、レタス1,740粒、キャベツ620粒をセルトレーにまきました。種まき培土を湿らせて、トレーに隙間なく詰めます。セルトレーの1穴に1粒ずつ置き、種が隠れる程度に覆土します。どちらも種が小さいのですが、特にレタスは薄くてすぐに風で飛んでしまいそうな種です。レタスは好光性種子で発芽に光も必要なので、覆土は薄めです。かといって、種が乾くのもいけないので、そっとかぶせていきました。

種まき後は、水やりをして、乾かないように新聞紙をかけておきました。
朝が寒かったため、ハウスを閉めて作業していましたが、午前11時半で、ハウス内が23度を超え、巻き上げを開けました。その後、日中もハウス内は20度を保ち、夕方16時半に苗床のビニールを閉めました。

キャベツは発芽適温が15~30度、レタスは15度~20度です。レタスは25度を越えると発芽不良になってしまうので暑さにも弱く、発芽に1番適正なのは18度~22度のようです。一昨日からの測定では、夜もこの温度を保てています。温度が適正であれば、3日ほどで発芽するはずです。緊張しますが、種のことを思ってこまめに見ていきたいです。
農業を中心となって見てくれている、まえちゃんが、畑にいつ定植できたらいいか、収穫する時期や、これまでの反省を踏まえて、種まきの日程を考えてくれています。3月から5月にかけて、春夏野菜の種まきをしていくのが緊張もするけれど、楽しみです。すべての野菜の発芽率がよかったらいいなと思うし、畑に定植するときに丈夫そうな苗が作れたらいいなと思います。
(まりの)