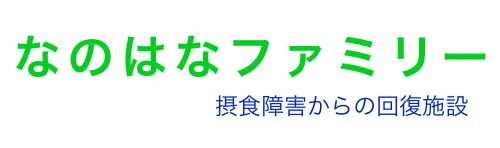3月7日のなのはな
ずっと、ずっと、この日を楽しみにしていました。
そう、桃の樹に看板がつく日を。
桃の収穫が終わった頃、お父さんやあんなちゃんたちと桃のまとめ会をしたとき、
「桃メンバーだけじゃなくて、初めて桃畑に行った子でも、一目見ただけで桃の品種が分かったらいいんだけどな」
とお母さんが話してくださり、その日から密かに、桃の樹に看板がつく日を夢見ていました。
そして、(次の夏には、すべての桃の樹に、看板をつけたい!)
そんな思いを胸に、この日まで、桃の看板作りを進めてきました。

手のひらサイズの木の板に、それぞれの樹の品種、植えた時期、収穫時期(早生、中生、晩生)が書かれた看板。
秋の夜の空き時間や、冬の作業が落ち着いた時に、みんなが手伝ってくれて看板に下書きをし、彫刻刀で彫って看板を仕上げていきました。
彫刻刀で彫られた桃の看板は、とても上品でしっかりとした佇まいで、1枚1枚がとても大切な作品に思えてきます。
桃の看板はこれから、何年もの間、外で雨や風、時には雪に直射日光を浴びることになるため、ニスを二重に塗ってあります。
今日は、つきちゃんと桃畑を回って、桃の樹1本1本に看板をつけて回りました。
あんなちゃんから、「腰より上の、目線の位置につけたらいいね」と教えてもらい、バインド線とマイカ線を使って、樹に看板を下げていきます。

スケールの大きい、私の何倍も背の高い桃の樹には、最初は手のひらサイズの看板はとても小さいように見えたけれど、実際に樹につり下げてみると、何とも可愛らしくて、今にも、桃の枝と枝の隙間からリスが「いらっしゃいませ!」と迎えてくれる……という絵が浮かんでくるほど、その看板が、桃のお店屋さんのようでした。
艶々とした可愛らしい桃の看板。これからの季節は、桃の摘蕾や摘果、袋がけに収穫など、メンバーも増えて桃の作業をする機会も増えるかと思うのですが、初めて桃の作業に入る子も、一目で品種や何年生の樹かが分かる看板がとっても嬉しいです。


みんなで大切に作った桃の看板。
看板作りを通しても、手伝ってくれたみんなが、桃の品種や畑について、より知ってくれたことが嬉しかったし、看板のついた桃の樹は、より愛情をかけられて大切に育てられているような雰囲気があり、今年も甘い桃の実がたくさん収穫できたらいいなと思います。
(ななほ)
***
キャプテンまえちゃん率いる、なのはな畝立て部。今日の部員は16人。
得意戦法は、追い越し方式。長い畝だって、馬跳びのように、お互いに距離をつなぐ追い越し戦法で、ちょちょいのちょい。
われらなのはな畝立て部は今日、約3反分の畝を立てました。


今日行ったのは春ジャガイモ用の畝立てです。
土寄せを必要とするジャガイモは、畝はベッド畝で、幅90センチ、畝間60センチのつくり。高さが15センチ上がれば十分であるため、面積はとても広いですが、スイスイと進みました。
コツは、頑張りすぎないこと。
高畝づくりに慣れているために、気が付いたらあるだけの土を上げようとしてしまいますが、軽めに、美しく、ジャガイモがここで大きくなるプロセスをイメージしながら作業を進めました。

長い畝も、みんなで追い越し方式で、少しずつ少しずつ進めました。なのはな1広い保育園前畑畑も、そうやってみんなで行なうと、目くらましの術みたいに、まったく長く感じませんでした。時には、追い越すときにその子の好きな色の当てっこクイズをしてみたり。
目の前の土に、目の前のひとかきに集中していると、あっという間に1畝ずつ終わっていきました。




そして4時。
山畑下を終えて、残すは山畑西。
上から見下ろした時のその広さは予想以上で、終わらせたい! と、思う一方、7割終わったらいいほうだ、と、弱気な自分もいました。
しかし、ここはやはり体育会系のバリバリ運動部。最後は負けん気が誰からもメラメラと。春の暖かさと、身体の内側からの暑さと、腰にたまってきた重さを感じながらも、絶対にあきらめたくない。
1日の強化合宿を終えるころには、5分で2畝を作るペースの、超ハイスピードにまで畝立て術を極めることができました。


最後の1畝まで終わったときは、まさに、「終わったーーー!」という気分でした。
世界中に声を上げたいくらい、とても達成感がありました。
最後のご褒美に、みんなと畦で腰を伸ばしたことは、本当に気持ちが良かったです。
(ちさ)

***